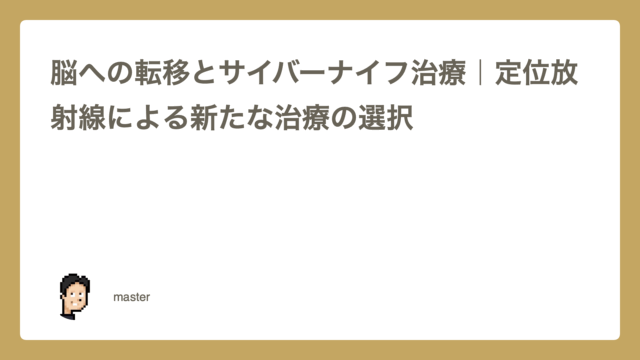――がんと共に生きるということ――
【第1章】はじまり|分子標的薬との出会いと最初の闘い
父が肺がんステージ4と診断されたとき、僕たち家族は大きな衝撃を受けた。けれど、そのとき医師は「分子標的薬が使える可能性がある」と丁寧に説明してくれた。いわゆる“がんゲノム異常”を狙い撃つ薬で、副作用が少なく、効果も期待できるという新しい治療法だった。
父に使用されたのは、タフィンラー+メキニストという組み合わせの薬。これは、がん細胞の増殖に関わる遺伝子のスイッチをピンポイントで抑え込む薬で、まさに“分子レベルの治療”と言われるものだ。
実際に治療を開始すると、肺の腫瘍は一時的に縮小し、体調も比較的安定していた。食欲も保たれ、散歩にも出かけられるほどだった。父は「すごい薬だな」と笑い、僕たちにも少し希望が戻ってきた。
しかし、がんはしたたかだった。数か月後、薬の効果は徐々に薄れ、再び全身のがんが進行を始めた。分子標的薬は「適合すれば適面によく効く」が、「いずれ効かなくなる時が来る」薬でもあった。医師も当初から「いつか必ず耐性が出る」と話していた。父は静かにうなずき、「次に進もう」と前を向いた。
分子標的薬は、父にとって最初の大きな武器となった。しかし同時に、がんと向き合う現実を僕たち家族に突きつけた治療でもあった。
【第2章】免疫療法の壁|ニボルマブ+イピリムマブとの日々
分子標的薬に耐性が出たあと、父は免疫療法に切り替えた。ニボルマブとイピリムマブという、Tリンパ球に働きかけてがんを攻撃させる薬の組み合わせだ。抗がん剤とも違い、がんそのものを直接叩くのではなく、“免疫の力”を高めるという仕組みの治療だった。
当初、医師からも「免疫療法は2〜3割に効果があるが、その人に効くかどうかは実際にやってみないと分からない」と説明された。副作用も、場合によっては命に関わるほど強いこともあると聞かされ、正直怖さがあった。
それでも、父は一歩を踏み出した。がんを治したい。少しでも長く、家族と過ごしたい。その思いが、治療の選択を支えていた。
しかし、免疫療法は父には奏功しなかった。
医師の言葉は静かだったが、その裏にある重みは痛いほど分かった。僕は帰りの車の中で、母が静かに涙を拭く姿を見て、胸が締めつけられた。
【第3章】脳梗塞の発症|突然訪れた危機と家族の決断
転機が訪れたのは2025年4月4日。母が自宅で父を着替えさせていると、わずかに身体がふらつくのに気づいた。歩き方や表情がいつもと違い、「おかしい」と直感した母はすぐに救急車を呼んだ。
搬送される途中、父の表情はみるみる変わり、右手が動かなくなっていった。
診断は「脳梗塞」。
場所や大きさによっては、命に関わることもあるし、後遺症が重く残ることもある。
数日後、転院し、かかりつけ医の病院で急性期リハビリが始まった。父の右手は動きにくくなり、歩行はできるものの、トイレや入浴には介助が必要になった。
この時期の母の献身は言葉にできないほどだった。病室で、母は父の右手をさすり続け、「また一緒に買い物に行けるようにしようね」と優しく声をかけていた。その姿は、僕にとって一生忘れない景色の一つになった。
【第4章】サイバーナイフ治療|脳転移との闘いと奇跡のような奏功
脳梗塞が落ち着いた後、あらためてMRI検査を行うと、脳内には複数の腫瘍が確認された。つまり、肺がんが脳へ転移していた。
医師は迷わず、サイバーナイフによる定位放射線治療を提案した。腫瘍の数が多すぎる場合は「全脳照射」も選択肢になるが、副作用が強く、生活への影響も大きい。父の場合は、幸いにもサイバーナイフで一つずつ正確に狙い撃ちできる範囲だった。
別の大病院で治療を行うことになり、僕と母が初めてその病院を訪れたとき、最新鋭の設備に圧倒された。放射線治療室は、まるでSF映画のようで、そんな環境で治療を受けられるのは不安の中にも安心感があった。
治療は数日間に分けて行われ、1日2箇所ずつ腫瘍を照射するというもの。担当医は日本国内でもトップレベルのサイバーナイフ専門医で、冷静に淡々と処置方針を説明してくれた。その落ち着きは、家族にとって何よりの支えになった。
治療後に撮影されたMRIには、はっきりと「腫瘍消失」と書かれていた。僕たちは思わず目を見合わせ、言葉にならないほどの安堵を感じた。父も静かにうなずき、「すごい時代だな」とつぶやいた。
【第5章】抗がん剤治療と日常の両立|変わらない生活のありがたさ
現在、父は3週間に一度、大学病院で抗がん剤治療を受けている。カルボプラチン+ペメトレキセドという標準的な組み合わせで、がんの進行を抑える治療だ。
点滴前にはステロイドや吐き気止めが投与され、副作用を抑える工夫がなされている。昔のように「抗がん剤=つらすぎて立てない」というイメージとは違い、医療は確実に進歩している。
白血球が下がる時期はあるものの、現在の父は食欲も十分で、むしろ少しふっくらしたようにも見える。母の工夫した食事が効いているのだと思う。味噌汁、煮物、魚、野菜。父が好むものばかりが綺麗に食卓に並び、母は「食べれれば大丈夫」と笑う。
日中は近所をゆっくり散歩し、庭に水をやり、新聞を読み、穏やかに過ごしている。外出は病院と少しの買い物程度に控えているが、それでも“普通の生活”と言える毎日を過ごせている。
【第6章】再発予防の注射と母の支え|見えない努力の積み重ね
脳梗塞を経験した父は、再発予防のために“血液をサラサラに保つ注射”を毎日行っている。本来であれば、医療機関に通って処置をしてもらうべき場面も多い。しかし、母は医師や看護師から丁寧にレクチャーを受け、手技を覚え、自宅で安全に注射を打てるようになった。
最初のころ、母はかなり緊張していた。当たり前だ。
“針を刺す”ことに対して、誰だって恐怖がある。
父も「大丈夫か?」なんて冗談めかして言っていたが、いざ母が針を持つと、言葉少なに腕を差し出した。その姿を思い出すと、どこか胸が熱くなる。
ふたりは夫婦として長い歳月を一緒に過ごしてきた。しかし、こんなふうに「生命の続く時間」を守る役割を母が担うようになったのは、きっと初めてだっただろう。
注射を終えると、母は毎回欠かさず消毒し、針の廃棄をし、日誌に記録を残している。
それは誰かに見せるためではなく、ただ父のために続けている仕事だ。
「これも私の役目だと思っているから」
母はそう言って笑うが、その背中には計り知れない緊張感と責任が積み重なっている。
父も、そのことを深く理解している。
照れもあるのか本人の口から直接は言わないが、看護師さんにだけ「うちの妻はすごいんですよ」と話していたという。母はその言葉を聞いて、そっと涙ぐんでいた。
日常のどこにも派手なドラマはない。
けれど、こうした小さな努力と支えの積み重ねこそが、父の今を守っている。
そして僕は、その光景をそばで見られることを、いま心からありがたいと思っている。
【最終章】これからの治療と、家族としての願い
父の治療は、これからも続いていく。
抗がん剤の投与間隔は3週間に一度。血液検査の数値次第では延期されることもあるし、次のステップに進む必要が出る可能性だってある。がんという病は、一度よくなったからといって油断できない。
しかし、僕は不思議と悲観していない。
なぜなら、いま目の前で生きている父の姿が、すでに強さそのものだからだ。
朝の光を浴びながらゆっくりと歩く姿。
孫たちの話題になると、表情をふっと緩めるあの瞬間。
そのすべてが、父の「生きようとする意志」に見えてしまう。
もちろん、これからの治療がどう運ぶのかは誰にもわからない。
抗がん剤が効き続ける保証もないし、別の治療に切り替える日が来るかもしれない。
再発、転移──そんな言葉は、家族であれば誰しも心の中でひっそりと警戒し続けている。
それでも僕は、ただ一つの願いを持ち続けている。
「父が今日を安心して過ごせる時間を、少しでも長く守りたい」
息子の入学式を一緒に見たい。
今まさに受験勉強を頑張っている娘が中学生になる姿を、一緒に祝いたい。
家族全員が揃って食卓を囲む、その“普通の日”を、一日でも長く届けたい。
病気は、人生を一変させる。
しかし、それによって手に入る気づきもある。
僕は父の姿を通して、“生きる”という言葉がどれほど尊いものかを痛感した。
これからも父の治療は続き、僕たち家族の支えも続く。
その過程のどんな瞬間も、失われることのない「人生のかけら」だと思っている。
そして僕は、こうして記録を残していくことで、父との時間を未来へ縫いとめようとしているのかもしれない。
父が生きてきた証を、家族の中だけでなく、僕自身の人生の中でも確かに刻んでおきたい。
これからも父は生き続ける。
僕たち家族は、その隣で支え続ける。
その姿こそが、きっと僕たちの“家族の物語”なのだと思う。