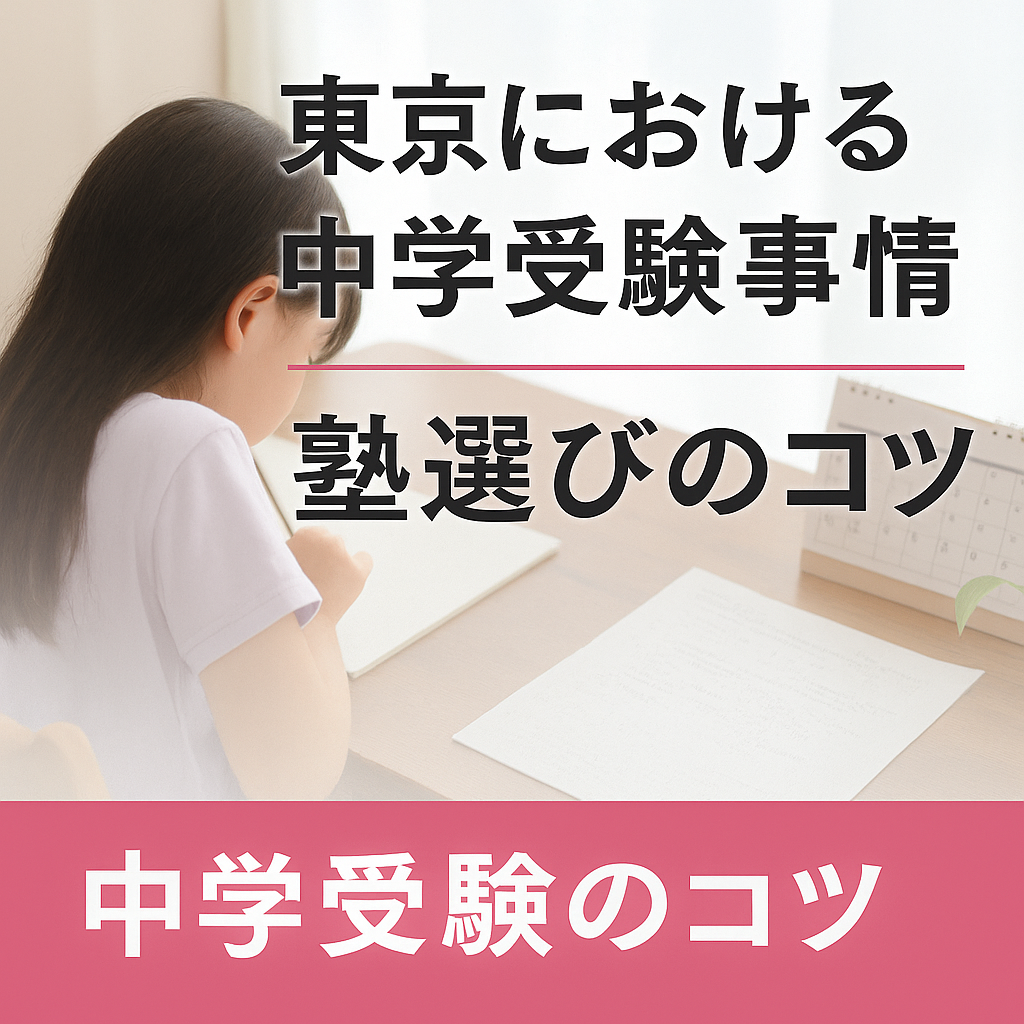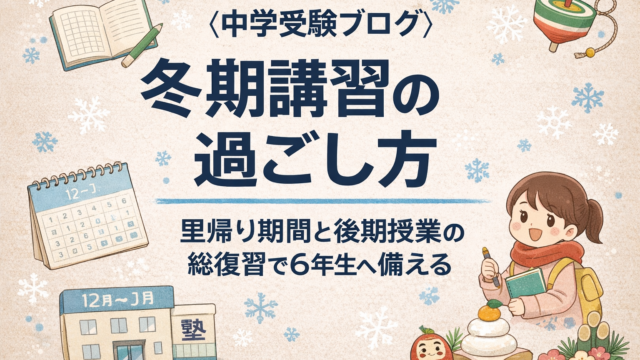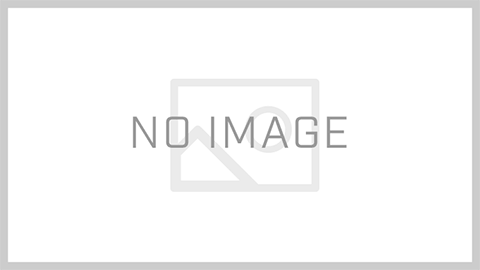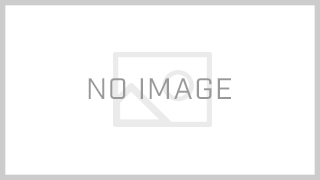小学5年生の娘と挑む東京の中学受験物語
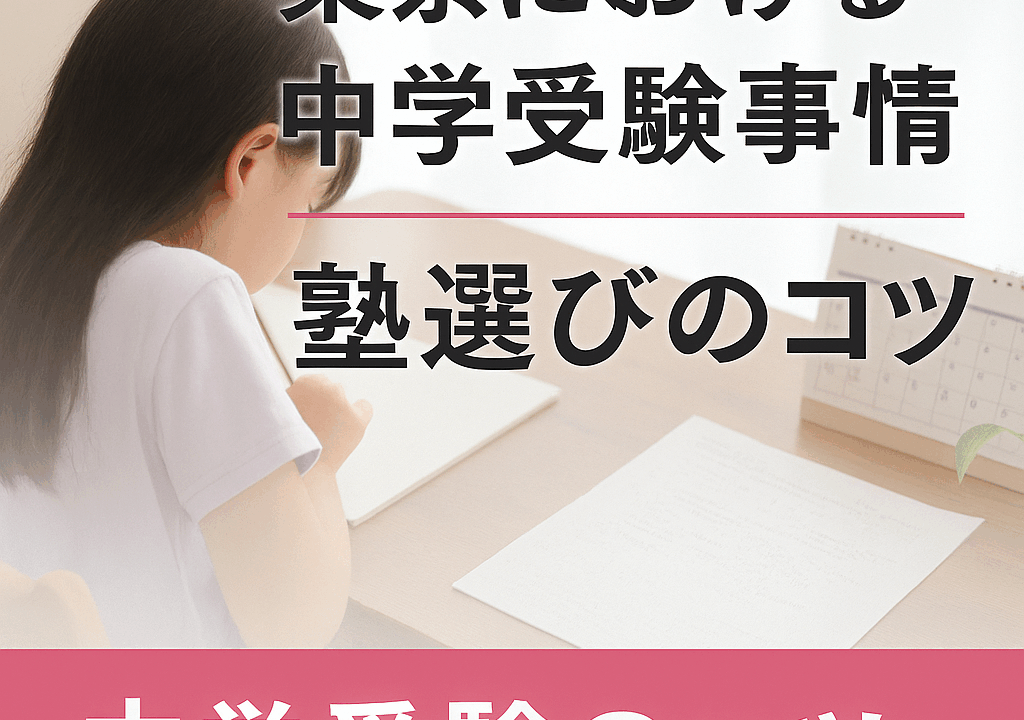
親子で歩む成長の記録。
序章:なぜ「受験」を選んだのか──地元中学を避けた理由
娘が小学4年生になった春、僕たちはある決断をした。「このまま地元の公立中学に通わせていいのか?」という問いに対し、明確な答えを出したかった。
僕の母校でもある地元の中学校は、特に荒れているというわけではない。だが、地元独特の空気感や生徒同士の雰囲気も、娘にとって良い刺激になるとは感じられなかった。無気力な空気の中で3年間を過ごすことを想像すると、娘の未来が閉じられてしまうような不安があった。
一方で、僕たちの周囲には私立中学に進学した家庭の子どもたちがいて、それぞれのびのびと自分らしい学びを見つけているように見えた。(完全な妄想かもしれないが、、、)
制服や通学距離、部活動の内容といった学校生活のディテールまで調べながら、「この子に合う環境とは何だろう」と夜な夜な話し合う日々が続いた。
幸いにも、僕たちの住むエリアは東京23区内で、比較的優秀な私立中学校が密集している。選ばなければ、多様な選択肢が広がっている。だからこそ、僕たちは「中学受験」という選択肢を真剣に考えるようになった。
第1章:東京の中学受験というジャングル──情報戦の始まり
中学受験は、まさに情報戦だった。友人たちの話を聞き、ネットの掲示板を読み漁り、本屋に並ぶ中学受験関連の本を片っ端から読み込んだ。SAPIX、日能研、早稲アカ、四谷大塚──塾だけでも十数種類。各校の偏差値帯や入試傾向、家庭との相性、校風や指導スタイル……知れば知るほど、「自分の子に合う塾とは何か」という疑問が膨らんでいく。
合格実績や広告だけでは読み取れない、塾の“空気感”や“テンポ”。保護者会に参加し、体験授業にも足を運びながら、徐々に見えてくるものがあった。中学受験の世界では、親の下調べと分析力も試されるのだと実感した。
“中学受験は親の受験”という言葉が頭をよぎった。まだ10歳の子どもに、これほどの競争を課すのかという葛藤もあったが、それ以上に「娘の未来のために、今しかできない選択をする」という信念が揺らぐことはなかった。
第2章:塾選びのドラマ──娘の気持ちと親の思惑
娘は最初、「東京個別指導学院」や「完全個別指導塾TOMAS」などの個別指導塾に通いたいと話していた。少人数制で質問がしやすく、先生とも打ち解けやすいというメリットは、彼女にとって大きな魅力だった。
しかし僕たち親の目には、少し違った不安が見えていた。先生との距離が近くなるほどに“甘え”が生じるのではないか──。特に娘は人懐っこい性格で、大人と仲良くなるのが上手い。だが、それが“緊張感”を失わせてしまうのではという危惧があった。
今まで学校の宿題しか経験のない娘には、いきなり大量の課題や、競争の中で生き残ることを強いる環境は酷だった。何事にも自分のペースでゆっくりとコツをつかんでいく娘、頑張り屋だけど、無理はさせたくない。勉強を嫌いになってほしくない。そんな気持ちも僕たちの判断に大きく影響した。
最終的に僕たちが選んだのは「日能研」。
- 週3回の通塾ペース
- 学習の進度にレベル分けあり
- 毎週の育成テスト、定期的な公開模試
- 解き直しや復習を重視したカリキュラム
娘にとって無理のないペースで、自信を積み上げていける環境。それが日能研だった。
第3章:最初はボロボロ──テストに追いつけない娘
最初の数か月、娘はまったく授業についていけなかった。毎週土曜の育成テストでは下位クラスをさまよい、答案用紙には赤ペンの×印が並んだ。公開模試でも偏差値40台を切ることが珍しくなかった。
塾から帰ってくるたび、娘はふてくされた顔をしていた。勉強が面白くなくサボることも多々あった。
僕たち夫婦も、どうすればよいのか分からなかった。塾に行かせているのだから、成績は上がるはず。そう考えていたのが間違いだった。
塾の授業スピードは想像以上に速く、どんどん進んでいくカリキュラムに娘はついていくのがやっとだった。宿題も多く、平日は疲れて眠くなり、土曜のテスト前には夜遅くまで勉強する日もあった。
それでも娘は「やめたい」とは言わなかった。その姿に、僕たちは親として踏ん張らなくてはと思わされた。
第4章:親は軍師、子どもは兵士──覚悟を決めた日
ある日、読んだ本の一節が僕たちの心を貫いた。
「中学受験において、子どもは兵士、親は軍師でなければならない」
つまり、作戦立案、戦略策定、補給やメンタルケアまですべて親の仕事。勉強は子どもがするものではあるが、その“環境”と“道筋”を整えるのが親の役目なのだと。
それから僕たちは変わった。
- 授業の翌日には、娘と一緒にその日の内容を復習
- 間違えた問題は、原因を一緒に分析し、再度チャレンジ
- 単元の復習は、週末に家族で「模擬授業」
さらに、塾の教材の内容を僕たちも読み込み、どの問題を優先すべきか、どの範囲を重点的に見直すべきか、隔週行われる育成テストではどのような問題が出題されるか。しっかりとした戦略を立てるようになった。
娘の部屋は、まるで塾のようになっていった。ホワイトボードを導入し、その日の勉強計画を書きだし、娘の机の横には僕ら専用の指導椅子が設置され、家庭が学習の場そのものに変わっていった。
第5章:少しずつ見えてきた希望──安定する点数
勉強の仕方が定まってくると、育成テストの点数も徐々に安定してきた。最初は50点以下だったテストも、今では平均点を優に超え最上位クラスの平均点をも超えることが増えた。
公開模試における偏差値は、依然として50前後と“中の中”。だが、それでいい。今はまだ、小学5年の夏。ここから1年かけてじっくり知識を定着させ、思考力を育てていく時間がある。
どんどん上がる成績に、娘も「最近テスト楽しい!クラスで表彰されるから!」と楽しそうだ。自信が少しずつ積み重なっている証拠だ。
その影響は学校生活でも表れていて、昔は「学校行きたくない」と言っていた娘が、今ではクラスの中心になり学級を運営するようになった。
家庭学習での“できた”という感覚。先生に褒められたときの誇らしい表情。そうした小さな変化が、娘の中に確かな成長を刻んでいた。
第6章:上には上がいる──それでも娘の努力を信じて
塾のクラスには、すでに偏差値60を超えるような強者たちがゴロゴロいる。同じ年齢で、これほどの努力と成果を出している子どもたちがいることに、正直なところ圧倒される。
でも、焦らない。
僕たちは僕たちのペースでいい。娘の成長は、誰かとの比較で決めるものではない。
成績は波のように上下するし、いつも結果が出るとは限らない。でも、確実に娘の“考える力”はついてきている。正解を出すことよりも、自分の言葉で説明できるようになることが、僕たちの目標になった。
最終章:この努力は、必ず未来に繋がっていく
娘は今、毎晩のように机に向かっている。解けない問題に悔し涙を浮かべることもあるが、諦めずに鉛筆を持ち直す姿は、誰よりも立派な“兵士”だ。
僕たちはその背中に、どんな偏差値の数字よりも大切な“姿勢”を見ている。
「この経験は、きっと君の人生の糧になる」
その過程で、スティーブ・ジョブズの言葉がふと思い出された。
“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.”
いま積み重ねている点は、きっと未来に線としてつながっていく。点と点を信じて進むしかない。
そう信じて、今日も僕たちは一緒に歩んでいる。中学受験という名の、短くも長い旅路を──。
道のりは決して平坦ではないけれど、点と点をつなぐその手を、僕は決して離さない。