【年金65歳まで納付】効果試算へ保険料5年延長、その影響とは?
厚生労働省は年金の将来の給付水準を点検する今年の「財政検証※1」で、自営業者らが加入する国民年金の保険料納付期間を現行の「60歳になるまでの40年」から「65歳になるまでの45年」に延長した場合の底上げ効果を試算する方針を固めました。
延長した場合、将来受け取る年金の水準低下を抑制できるとされています。今夏に検証結果を公表し、年末までに実施の可否を決めるとのことで関係者が11日明らかになりました。
※1財政検証とは・・・財政検証とは、公的年金の長期にわたる財政の健全性を定期的にチェックするために行う検証のことです。 おおむね100年にわたって年金財政の均衡を図ることを目的として財政検証が行われます。 公的年金制度は長期的な制度であり、持続可能な制度になっていることが重要です。
延長によって保険料負担が増える側面もあり、反発が出る可能性があります。
現行の国民年金保険料の納付期間は、20歳以上60歳未満の40年間。65歳になるまでの45年間に延長すると、受け取る年金額は増えます。今回の財政検証では、制度改正による影響を見る「オプション試算※2」として、延長した場合に将来世代が受け取る年金の給付水準がどう変化するかを算出する見通し。
※2「オプション試算」とは、日本の年金制度において、将来受け取る年金額を自分の状況に応じてさまざまな条件で試算することを指します。このシステムを利用することで、年金受給開始年齢の選択や、加入期間、所得レベルなど、異なる条件下での受給額がどのように変化するかを事前に確認することが可能です。
このほかにもいくつかの見直し検証が行われる予定とのことです。
- パートら短時間労働者の厚生年金加入要件の緩和
- 厚生年金から国民年金への財源振り向け
- 65歳以降の賃金に応じて厚生年金が減る「在職老齢年金制度」の見直し
これらの見直しにより現役世代の負担額は増加するものの、年金制度の持続可能性を考慮する際においては、重要な見直しとお受け取っています。一時的な負担額を受け入れ、年金基金の運用元本に回すことができれば将来的なリターンも見込める可能性も考慮すると、一方的な否定意見ばかりではないように思っています。日本はよく少子高齢化先進国とか、衰退先進国と言われていますが、日本が先陣を切って少子高齢化社会の手本を作っていく様をみたいですね。
日本の年金制度とは
日本の国民年金制度は、基本的な公的年金制度の一つで、全ての国民を対象としています。この制度は、老後の生活の安定を図るため、また障害を持った場合や死亡したときにその家族を支援することを目的としています。
国民年金は以下の三つのカテゴリーに分けられます:
- 第一号被保険者:20歳から60歳までの自営業者、フリーランス、学生、無職など、職場の厚生年金に加入していないすべての人が該当します。これらの人々は自ら年金事務所に申し込み、保険料を支払う必要があります。
- 第二号被保険者:厚生年金保険の加入者です。主に会社員や公務員がこのカテゴリに該当し、彼らは厚生年金保険と国民年金の両方に自動的に加入します。厚生年金は国民年金をベースとし、さらに雇用者との共同出資による追加の恩恵を提供します。
- 第三号被保険者:第二号被保険者(主に配偶者が会社員や公務員である場合)の配偶者で、自身は収入がないか少ない人々です。これらの人々は第二号被保険者の配偶者として自動的に国民年金に加入され、保険料は第二号被保険者が支払います。
国民年金の保険料は定期的に見直され、現在の月額は約16,540円(2023年時点)。受給資格は、加入期間が一定期間以上あることが条件で、一般的には25年以上の加入が必要です。
国民年金は、将来的な経済的保障を提供するための基本的な制度であり、すべての国民が何らかの形で関与しています。
国民年金崩壊のシナリオとその背景
国民年金制度の「崩壊」に関する噂について、最近はあまり耳にしなくなりましたが、主に次のような懸念から生じています。
国民年金制度の崩壊に関する噂
- 高齢化社会の進行:日本は世界でも顕著な高齢化社会であり、高齢者の比率が増加することで、年金受給者数が増え、年金制度への負担が増大しています。これにより、将来的に支払い能力に問題が生じるという懸念があります。
- 少子化の進行:出生率の低下により、労働力人口が減少し、将来的に年金を支える若年層の数が減少していきます。これにより、現役世代と高齢者世代のバランスが崩れ、年金制度の持続可能性に影響を及ぼす可能性があります。
- 経済状況の変動:経済成長の鈍化や市場の変動は、年金基金の運用成果に直接影響を与え、制度の安定性に悪影響を及ぼすことがあります。
対応と解決策
結論としては崩壊するはずもないのです。確かに少子高齢化が進む日本は人口ピラミッドの形状からして、数少ない若い人々が増え続ける高齢者を支えていくように見えるかもしれません。しかしこう言った問題に対して、完璧ではないにしてもしっかりと対策を行なっており、定期的な見直しがなされています。
- 政策の適応:政府は年金制度の財政状況を定期的に見直し、必要に応じて保険料の調整や受給資格年齢の見直しなど、柔軟な政策調整を行うことが求められます。これにより、制度の持続可能性を高めることが可能です。今回の納付期限の延長についても政策見直しの一環となり、年金システム存続の一助となります。
- 経済成長の促進:経済を活性化させ、より多くの雇用を創出することで、年金制度に貢献する労働力人口を増やし、制度の基盤を強化することが重要です。また、年金基金の運用方針を見直し、リスクを適切に管理しながら収益性を向上させることも必要です。定年年齢の引き上げなどがこれにあたります。
- 個人の責任の増大:国民一人ひとりが自身の将来の資金計画についてもっと積極的に考え、個人年金や貯蓄、投資など、自己責任における準備を整えることが推奨されます。これにより、公的年金に依存する度合いを減らし、個人の金融リスクを分散できます。個人の金融リスク分散に関しては国が推奨している新NISAもその一環となり「積極的に個人の資産を増やし年金受取額の減少に備えるように」との国からのメッセージとも受け取れます。
- 社会全体の意識改革:少子化対策やライフスタイルの多様化を進めることで、社会全体としての持続可能な発展を目指すことが重要です。それには、働き方の改革や女性の社会進出の促進、家庭と仕事の両立支援など、幅広い社会制度の改善が求められます。
以上のように、国民年金制度の持続可能性には複数の課題がありますが、これらに対する具体的な対策と政策の実施により、崩壊のリスクを最小限に抑えることができます。
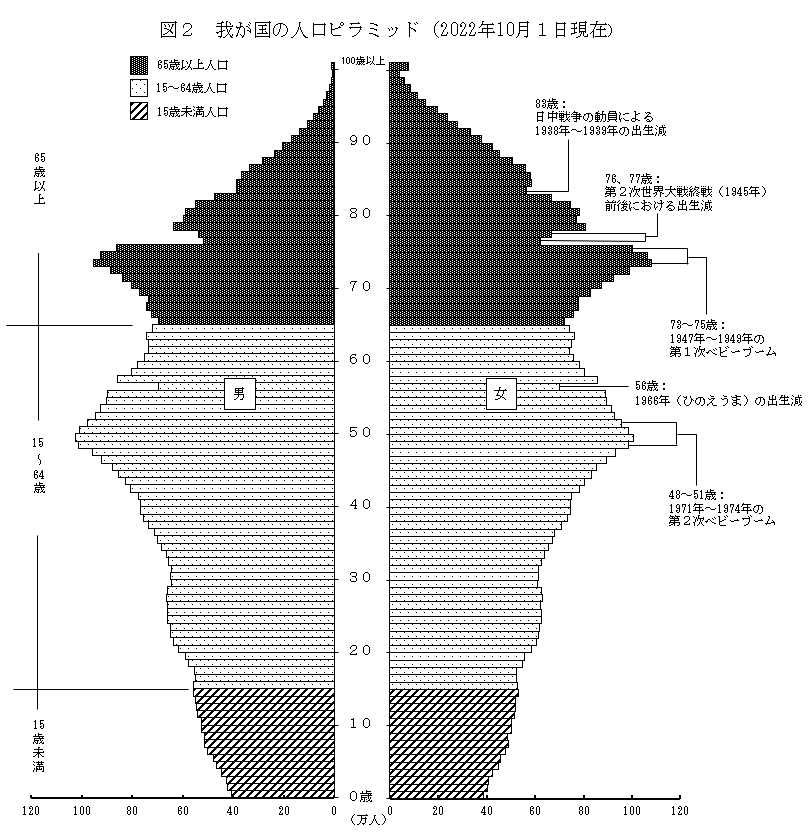
国民年金の財源とは
日本の年金制度の財源は主に以下の三つから成り立っています。我々の目に見えるところでは給料から天引きされる保険料が一番身近ですが、それらを運用し運用益も年金の財源として充てられています。
- 保険料:年金制度の主要な財源で、全ての被保険者が支払う保険料がこれに該当します。国民年金の場合、自営業者やフリーランス、無職などの第一号被保険者、および厚生年金に加入している第二号被保険者、そしてこれらの被保険者の配偶者である第三号被保険者が関わっています。厚生年金においては、雇用者と労働者が共同で保険料を負担します。
- 国庫負担金:政府が年金基金に直接出資する形の財源です。これは公的負担として年金制度を支えるために、税金を用いて国庫から年金基金へと資金が供給されます。国庫負担の比率は政策によって変動することがありますが、国民年金の場合、国庫からの補填が一定割合で行われています。
- 運用益:年金基金が市場で投資を行い、その運用結果として得られる利益も財源の一つです。日本の年金資金は国内外の株式、債券、不動産など様々な資産に投資され、これによる運用益が年金給付の財源に充てられています。なお、積立金残高は4兆6,020億円(2023年3月末時点)となっており、安定的な利回りも確保されています。
これらの財源は、年金制度の安定性を保つために重要であり、特に少子高齢化が進む中での財政的な持続可能性を確保するためには、これらのバランスを適切に管理することが求められます。
新NISAの活用と資産形成
2024年から開始された新NISAは、長期的な投資を促進するための制度です。これにより、株式や投資信託などを通じて、より長期間にわたり資産を増やすことが可能となり、老後の年金受給額が仮に減少したとしても十分な蓄えによって、自身の心配事を回避することができるようになります。改めて新NISAのメリットを以下の通り振り返ってみます。
- 税制上のメリットが大きい: 新NISAのもう一つの魅力は、投資から得られる利益(配当金や売却益)が非課税になる点です。この非課税措置により、税負担を気にすることなく、より多くのリターンを手元に残すことができます。これは特に長期的に積み上げる投資には大きなアドバンテージとなります。
- 資産の多様化とリスク分散が可能: 新NISAを活用することで、様々な金融商品への投資が可能となります。国内外の株式はもちろん、債券やREIT(不動産投資信託)など、幅広い商品を選択できるため、資産の多様化とリスクの分散が図れます。これにより、市場の変動に対するリスクを軽減しつつ、効率的な資産運用が期待できます。
- 投資意識の向上と教育への寄与: 新NISAを利用することで、投資に対する知識や意識が高まることが期待されます。非課税というメリットを活かして少額から投資を始めることができるため、投資初心者でも安心して市場に参入しやすくなります。また、定期的な投資やポートフォリオの見直しを行うことで、より効果的な資産管理を学べるため、金融リテラシーの向上にも繋がります。
まとめ
僕は前の記事でも書いていますが、日々の節約に励みながら、資産形成を行っています。モノを減らし、身の丈に合った生活を心がけています。また、無駄なお金を使わずに日々の小さな出費が積み重なることも忘れずに過ごしています。
そして、節約だけでなく節約したお金に働いてもらうことも忘れていません。当然ながら資産運用も重要です。資産運用によって、将来のための貯蓄を増やし、セミリタイアを目指すことも可能と考えています。
僕の好きな書籍タイトルに「JUST KEEP BUYING」というフレーズがあります。淡々と株式を買い進めると言ったニュアンスで使用されています。
僕はこれに倣い淡々と投資を進めています。上記の本は非常に良書となっていますので、別の記事でご紹介したいと思います。
当ブログの節約情報や投資情報はこちら





