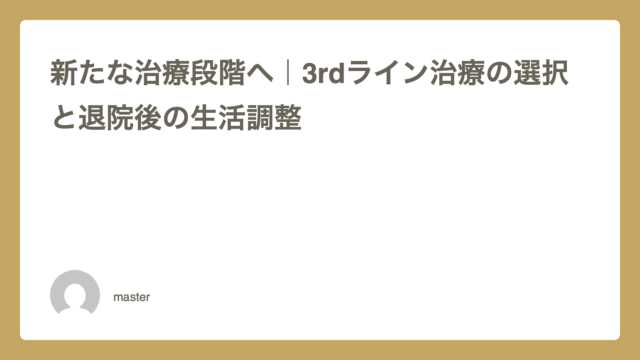アサヒビールとサッポロビールが、度数8%以上のいわゆるストロング系缶酎ハイの新商品を今後は発売しない方針を固めましたね。
キリンビールも販売について慎重な姿勢だとか。
僕が眺めているX(旧Twitter)でもストハイユーザーは一定数いましたが、最近影を潜めている気がします。
飲酒と健康障害との関係性について、世界保健機関(WHO)はアルコールの健康リスクを警戒しています。
厚生労働省も飲酒のリスクは酒の量ではなく、純アルコール量が重要だとして、「健康日本21」で「節度ある適度な飲酒」を推奨。
アルコール分解酵素が弱い女性は、その半分程度の10gが適切とされています。
健康志向の高まりやコロナ流行により、アルコールの国民1人あたりの摂取量は減少していますね。
外飲みから家飲みへのシフトもあり、家庭内で一気に酔いが回るような飲み方は難しくなっています。
さらに、「ソバーキュリアス(飲まない生き方)」の浸透などもあり、強い度数のアルコールに対する懸念が消費者の間に広まっていることがストロング系市場の減少の背景となっています。
企業側にも消費者の健康を考慮して商品力を高める責任が求められており、低アルコール飲料の新商品開発が活発化することで、新たな競争が始まっていると言えるでしょう。
日本は路上での飲酒が許されている先進国であり、アルコール機会や価値の変化に対応する姿勢が求められています。
私自身、お酒はあまり飲まないのですが、今後喫煙と同様肩身の狭いコンテンツになっていきそうですね。