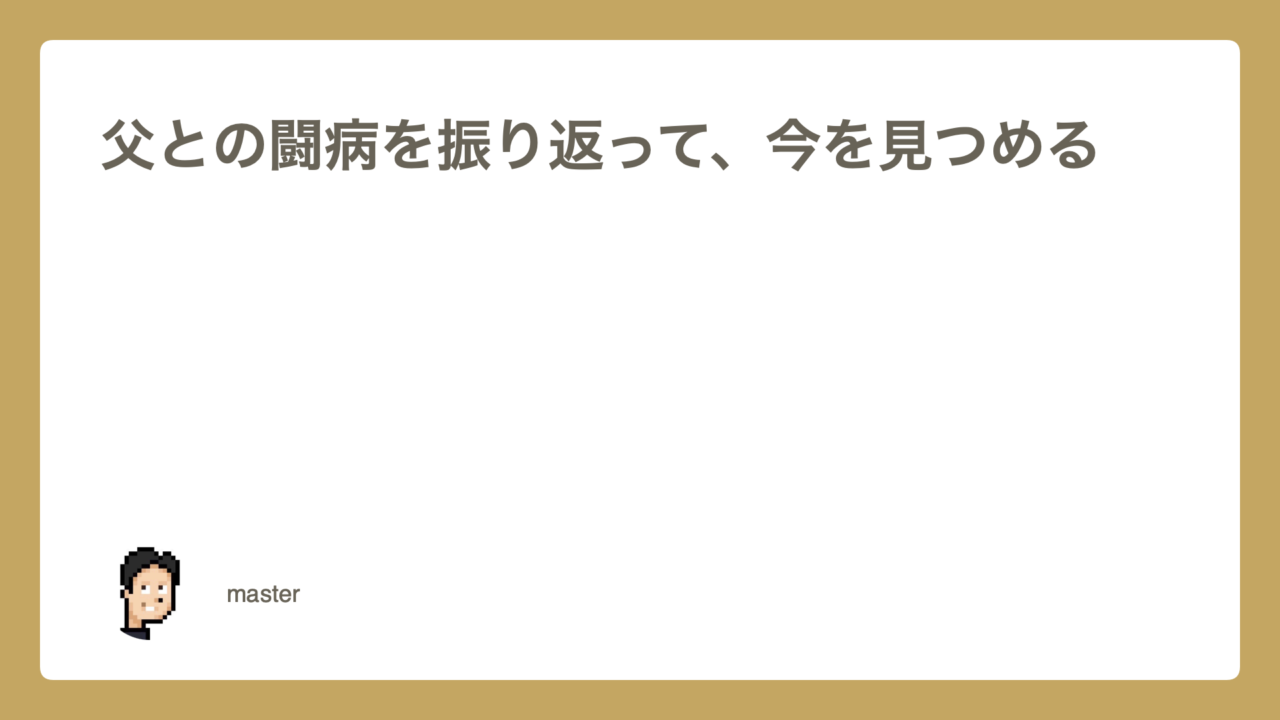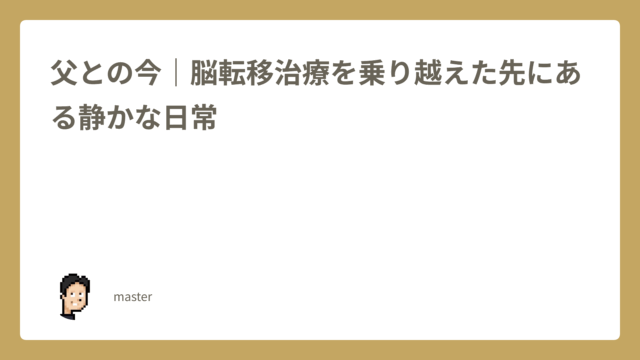――がんと共に生きるということ――
第1章:あの日、突然に──診断の衝撃
父が肺がんステージ4と診断された日のことを、僕は今でも鮮明に覚えている。
あの時、病院の空気は妙に冷たく、医師の一言一言がゆっくりと耳に届いた。
「肺せんがんです。骨やリンパにも転移しているステージ4です。」
父は淡々と受け止めるように聞いていたが、その表情の奥には、言葉にできないものが渦巻いていたはずだ。
僕も母も、ただ黙って頷くことしかできなかった。
振り返れば、その直前までの父は、ごく普通の生活をしていた。
庭の草木に水をやり、新聞を読み、日々の生活の小さなルーティンを淡々と続けていた。
多少の咳はあったが、年齢相応のものだと誰もが思っていた。
だからこそ、検査結果の現実は残酷だった。
「なぜ、今なのか」
「もっと早く気づけなかったのか」
そんな問いが心をよぎったが、誰を責めることもできなかった。
その日を境に、家族の時間の流れは確実に変わった。
“これからどれだけの時間が残されているのか”という意識が、静かに僕たちの生活に入り込んだ。
第2章:免疫療法への希望と、その限界
最初に提案された免疫療法(ニボルマブ+イピリムマブ)は、僕たちにとって光のような存在だった。
治療の資料を読み漁り、「3割ほどの人に効果がある」という言葉に、僕は知らず知らずのうちに期待を寄せていた。
父も、「やれることは全部やる」と静かに覚悟を決めていた。
最初の数回は、副作用こそあれど、治療を続けられる状態が続いた。
しかし、期待していた腫瘍の縮小は見られず、さらに脳内出血によって治療の継続は不可能となった。
医師は冷静に話してくれたが、その冷静さが逆に僕たちの胸に重くのしかかった。
「免疫療法は効かなかった」
「次の治療に移る必要がある」
希望から現実への落差は、想像以上に大きかった。
父の前では気丈に振る舞ったが、帰りの車の中で、母は静かに涙を流した。
僕にとっても、この段階が「父の病気と本気で向き合う入り口」になったのだと思う。
第3章:3rd Line治療への挑戦──カルボプラチン+ペメトレキセド
免疫療法が終了し、次に選択されたのが抗がん剤治療だった。
父は静かに医師の言葉を聞いていたが、その目には微かな不安と、同時に強い決意が宿っていた。
カルボプラチンとペメトレキセド。
標準的ではあるが、決して楽な治療ではない。
頻度は3〜4週間に1回、点滴投与。
数回の投与後、効果が出れば維持療法に移行できる。
副作用として予想されていた吐き気や倦怠感は、薬の進歩や事前の処置のおかげで、父は思ったほど大きく崩れずに済んだ。
母は毎日、栄養のある食事を工夫し、少しでも体力を保てるように細かく気を配っていた。
僕も実家に寄るたび、父の様子を見ては少しだけ安心し、また少しだけ不安になる。
その繰り返しだった。
家族全員が、治療のたびに小さな山を越えていくような感覚だった。
第4章:脳への転移とサイバーナイフ治療
そして、さらに重い事実が判明する。
脳への転移。
「脳」という言葉だけで、全身から血の気が引くようだった。
失語、視野障害、認知機能の低下……
恐ろしい未来ばかりが頭をよぎった。
しかし、そこで提案されたのがサイバーナイフ治療だった。
最新鋭の定位放射線治療。
「ピンポイントで腫瘍を焼き切る」
その説明は非常にシンプルだったが、同時に圧倒的な精密さを感じさせた。
治療は1日2か所ずつ、数日間に分けて行われた。
父は静かにその治療を受け、家族は毎回、祈るように結果を待った。
そして、治療後のMRI。
「腫瘍は消えています」
医師のその言葉は、今思い出しても胸が熱くなる。
家族全員の中に、久しぶりに大きな光が射し込んだ瞬間だった。
第5章:穏やかな日常、続く治療
2026年1月現在、父は月3回ほどのペースで大学病院に通い、抗がん剤治療を続けている。
カルボプラチン+ペメトレキセドにより、がんの進行は抑えられているという。
食欲は十分にあり、母の丁寧な料理のおかげで体重もほんの少し増えた。
肌つやも良く、パッと見では病人とは思えないほどだ。
家では、毎日欠かさず血液をサラサラにする注射を母の手で行っている。
これもまた、家族の静かで大切なルーティンの一つになった。
これだけ見ると、いつもの日常と変わらないようにも思える。
しかしその裏で、父は確かに病と闘っている。
その事実を家族全員が理解しているからこそ、些細な時間の尊さが胸に染み入る。
第6章:変わらないようで、確かに変わっていく日常
父は今も、庭に水をやり、新聞を読み、近所を散歩している。
この生活は、父にとって「生きている実感」そのものなのだと思う。
ただし、人混みは避け、手洗いとうがいは欠かさない。
免疫力が下がっているからこそ、ほんの小さな風邪でも命取りになる可能性がある。
それでも父は落ち込むことなく、むしろ以前より明るく、冗談さえ口にするようになった。
穏やかな顔つきで、自然体のまま過ごしている。
母もまた、父の生活を支えながら、時には愚痴をこぼし、時には笑いながら、家族として新しい日常を築いている。
そして僕も、父のその姿を見ながら、「まだ一緒に歩けるのだ」という小さな安心を胸に、定期的に実家へ足を運んでいる。
年末に起きた想定外|右足の痛みが示していたもの
■ 変わらない日常のようでいて、日常ではない
抗がん剤治療は、3週間に一度のペースで淡々と続いていた。通院し、処方を受け、採血で数値を見て、体調を整えて帰る。外から見れば、父はいつも通りの生活を送っているように見えたと思う。
もちろん、がんが消えたわけではない。治療は続いている。身体の内側では常に“病魔”と向き合っている。それでも父は、日常をできるだけ日常のままに保とうとしていた。近所の散歩を続け、食事を摂り、新聞を読み、必要なときは病院に行く。そんな時間が積み重なっていた。
僕たち家族も、その「穏やかに見える日常」に、どれほど救われていたか分からない。
■ 12月初旬、右足の痛み
しかし12月の初旬、父が右足の痛みを訴えた。
言い方は淡々としていたが、痛みの種類ははっきりしていた。「筋肉痛というより、肉離れみたいな痛みだ」という。ちょうどその頃、父はストレッチを新しく始めていた。だから最初は、誰もがそう思った。筋を痛めたのだろう、と。
年末が近づくと、身体は無理がききにくい。寒さで筋も固くなる。少し張り切りすぎたのかもしれない。そうやって、痛みを“日常の延長”として処理しようとした。
けれど、その痛みは、日常の延長ではなかった。
■ 原因は「内出血」だった
父は脳梗塞の再発予防として、血液がサラサラになる薬を使用している。血栓を作らせないための、必要な治療だ。父にとっては、命綱のような薬でもある。
だが、その薬が、別の形で父を苦しめることになった。
右足の内部で、内出血が起きていたのだ。しかも、血液がサラサラであるがゆえに、体内での出血は簡単には止まらない。結果として、右足はみるみる腫れ上がり、パンパンになってしまった。
外から見て分かるほどの腫れ。痛み。熱を持ったような違和感。母の「おかしい」という直感は、正しかった。
そして父は、すぐに入院することになった。
■ 「ゼリー状になった血液」と、待つしかない時間
入院後、医師から説明を受けた。右足に滞留した血液はゼリー状になっており、基本的には筋肉が自然に吸収していくのを待つしかないという。
“待つしかない”
この言葉は、闘病の中で何度も出てくる。何かをすれば改善する、努力すれば進む、そういう世界とは違う。医療は進歩している。それでも、身体の回復には、どうしても時間が必要な場面がある。
特に今回のようなケースでは、焦りは禁物だ。急げば急ぐほど、余計に傷を広げる可能性もある。だから待つ。待って、身体が吸収するのを待つ。
ただ、その「待つ時間」が、当人にとってはとても長い。
■ 年末の病院という場所
父は年末の雰囲気を病院で過ごすことに、不満を漏らしていた。
その気持ちはよく分かる。年末は、家にいるだけで少し気持ちが浮く。テレビをつければクリスマスや大掃除・年越しの特番が流れ、スーパーには正月の食材が並び、空気が「区切り」に向かっていく。
そんなまさにクリスマスに病院のベッドの上にいるのは、窓の外の世界から置いていかれるような感覚があるのかもしれない。しかも父は、母と一緒に出かけ、買い物をし、食事をするのが大好きである・だからこそ、漏れ出た不満の言葉が、逆に胸に残る。
父だって帰りたいのだ。家にいて、いつもの日常を送りたいのだ。病院で年末を過ごしたい人なんていない。
でも、仕方がない。
身体は、待つしかない時間に入ってしまった。
■ それでも願うことは一つだけ
この一件で、改めて思う。がん治療は、がんだけと戦うものではないということだ。
脳梗塞の予防をしながら、抗がん剤を続けながら、身体の別のリスクとも折り合いをつけていく。何かを守るための治療が、別の痛みを生むこともある。そのバランスの上に、父の日常は成り立っている。
僕たちにできるのは、状況を受け止めて、日々を支えることだけだ。焦らず、過剰に悲観せず、でも軽くも見ず、淡々とやるべきことを重ねていく。
幸いにも、年越しを待たずして父は退院できることとなった。
年末に重なる娘の誕生会にも来てもらい、一緒にバースデーソングを歌うことができた。
この何気なく過ごすわずかな時間が今はかけがえのない時間に感じる。
時間は不可逆で、過去に遡ることはできない。
そんなことを思いながら毎日を大事に過ごしていこうと思っている。