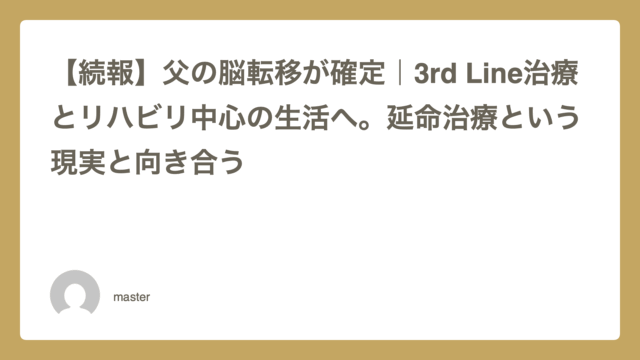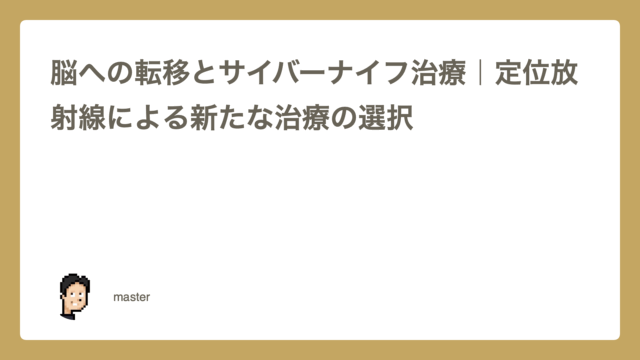父が肺がんステージ4と診断された話2

2023年4月に僕は父の病状を初めて耳にした。いわゆる肺がんステージ4である。そこからもう直ぐ2年が経とうとし、治療が新たなステージへ向かうとのことなので、自分自身の気持ちの整理と同じ境遇の人たちへ情報共有ができるように記事にした。また2023年に病気が発覚した時の話は、こちらの記事に詳しく書いている。
父に診断された病名は「肺腺癌 cT3N3M1c stage IVB」となっており、骨やリンパ節への転移が認められている状態。なお、「cT3N3M1c stage IVB」の表記はそれぞれががんの進行度合いを示すものになっており、こちらのHPに詳しく書かれており、参照させていただき以下の通り整理してみた。
T3は、充実成分径>5cmでかつ≦7cm、または充実成分径≦5cmでも以下のいずれかであるもの、同一葉内の不連続な副腫瘍結節、壁側胸膜、胸壁(superior sulcus tumorを含む)、横隔神経、心膜のいずれかに直接浸潤。N3は、がんのある肺と反対側の縦隔、肺門、同じ側あるいは反対側の前斜角筋(首の筋肉)、鎖骨上窩(鎖骨の上のくぼみ)のリンパ節への転移がある。M1cは、肺以外の一臓器または多臓器への多発遠隔転移がある。とのことで、なるほど要はたくさん転移しているそうだ。
父はBRAF遺伝子※が陽性であったため、2023年5月から分子標的薬(タフィンラーメキニスト)※による治療を開始したが、現在はその効果が見られなくなっている。さらに、右頚部リンパ節腫大と鎖骨上窩リンパ節腫大、右肺の病巣が拡大するとともに胸水の貯留も確認されており、胸水の細胞内にもがん細胞があるとわかった。
- ※RAF(ラフ)とは、細胞の増殖に関わるタンパク質のひとつで、RAFタンパク質には、「ARAF(エイラフ)」、「BRAF(ビーラフ)」、「CRAF(シーラフ)」の3種類があります。3種類のRAFタンパク質を作り出す遺伝子のどれかひとつに変化が起こると、通常とは異なる働きを持つRAFタンパク質が作られ、必要のないときにも細胞が増殖し、がんが発生しやすくなると考えられています。引用:中外製薬HP
- ※タフィンラー(ダブラフェニブ)とメキニスト(トラメチニブ)は、BRAF遺伝子に異常があるがんの治療に使われる分子標的薬である。BRAF遺伝子に変異があると、がん細胞が増殖し続けてしまうが、タフィンラーはこの異常な働きを抑え、メキニストはさらにその先の増殖信号を止める役割を持つ。この2つを組み合わせることで、がん細胞の成長を強力に抑え、治療効果を高めることができるとのこと。
この治療法は肺がんや黒色腫(メラノーマ)に使われ、がんの進行を遅らせる効果が期待されている。ただし、副作用として発熱がよく見られ、疲労感や皮膚の発疹、関節痛、高血圧なども起こることがある。長期間の使用では、心臓や目に影響を与える可能性もあるため、定期的な検査を受けながら治療を続けることが大切とされている。
一方で分子標的薬での治療は、通常9ヶ月の効果が平均的とのことだが、父の場合は1年半以上効果が持続し、分子標的薬による進行抑制は非常に効果的であったと理解している。
本薬は、非常に高額な薬で毎月150万円ほどかかるが保険適用薬で高額医療費助成により、月々の負担は10万以下で賄えていた。日本の医療保険制度はかくも有難いものであるかと再認識した。
そんな中、分子標的薬の治療に劇的な効果が見られなくなってきたため、今後の治療方針として、抗癌剤と免疫療法を組み合わせた2nd line(今までの治療の次段階)治療を行うことが決定された。
候補となる薬剤の組み合わせとしては、
「カルボプラチン+ペメトレキセド+ペンブロリズマブ」
「カルボプラチン+ペメトレキセド+デュルバルマブ+トレメリムマブ」
「ニボルマブ+イピリムマブ」
の3種類が挙げられている。
免疫療法は、人の体に本来備わっている免疫の力を利用して癌を攻撃する治療法である。
私たちの体には、ウイルスや細菌、そして癌細胞のような異常な細胞を見つけて排除する仕組みがあり、その中心的な役割を担っているのが「Tリンパ球」と呼ばれる免疫細胞である。Tリンパ球は、体の中を常に監視し、異常な細胞を見つけると攻撃を仕掛けて排除しようとする。しかし、癌細胞はこの攻撃から逃れるために特殊な仕組みを持っている。
その仕組みの一つが「PD-L1」と呼ばれる蛋白質である。癌細胞の表面にはPD-L1という物質が存在し、これがTリンパ球の表面にある「PD-1」という部分と結びつくことで、Tリンパ球の働きを弱めてしまう。つまり、本来ならば癌細胞を攻撃するはずのTリンパ球が、PD-L1の働きによって「この細胞は攻撃しなくていい」と誤認してしまい、結果として癌細胞が免疫の攻撃を逃れて成長を続けてしまうのだ。
免疫療法では、この「PD-L1とPD-1が結びついてTリンパ球の働きが弱まる」という仕組みを阻止することで、Tリンパ球が再び正常に働けるようにする。具体的には、「PD-L1抗体」や「PD-1抗体」といった薬を用いることで、PD-L1とPD-1が結びつくのを防ぎ、Tリンパ球が癌細胞をしっかりと認識し、攻撃できるようにするのである。これにより、免疫の力を活性化させて癌を攻撃するのが免疫療法の基本的な考え方である。
ただし、免疫療法にはメリットだけでなく、副作用のリスクもあることを理解しておく必要がある。
この治療は、免疫の働きを強くすることで癌を攻撃する仕組みだが、免疫が過剰に活性化しすぎると、正常な細胞まで誤って攻撃してしまうことがある。これは「自己免疫反応」と呼ばれる現象で、本来ならば自分の体を守るはずの免疫が、自分自身の組織や臓器にダメージを与えてしまう状態を指す。
免疫の暴走によって起こる可能性のある副作用はいくつかある。例えば、肺に炎症が起こる「間質性肺炎」という病気がある。これは肺の組織が傷つくことで、息苦しさや咳が出るようになり、悪化すると呼吸が困難になってしまう。
次に、「甲状腺機能障害」もよく見られる副作用の一つである。甲状腺はホルモンを分泌して体の代謝をコントロールする重要な器官だが、免疫の異常によって働きが乱れると、疲れやすくなったり、体重が急に増減したりすることがある。
また、腸に炎症が起こる「大腸炎」になると、下痢や腹痛、血便といった症状が現れることがあり、重症化すると腸が大きくダメージを受けてしまう。
さらに、「肝機能障害」が起こると、肝臓が正常に働かなくなり、だるさや黄疸(皮膚や白目が黄色くなる症状)を引き起こすこともある。
特に、免疫療法の中でも「ニボルマブ」と「イピリムマブ」という二つの薬を組み合わせた治療法では、これらの副作用が重くなるリスクが高まると報告されている。
具体的には、重度の皮膚障害が起こる確率は約4%、胃腸に問題が生じる確率は約2%、肝臓に影響が出る確率は約8%、ホルモンのバランスが崩れる「内分泌障害」は約3%、腎臓がダメージを受ける確率は約0.7%とされている。
これらの副作用が現れた場合、早めに適切な治療を行うことがとても重要である。もし対応が遅れると、症状がどんどん悪化し、命に関わるほど危険な状態になってしまうこともある。
そのため、免疫療法の副作用が疑われる症状が出た際には、速やかに医師に相談し、必要に応じて治療を受けることが求められる。治療としては、過剰に活性化した免疫を抑えるために、ステロイドの内服薬や点滴を使用することが一般的である。これにより、免疫の働きを落ち着かせて、副作用の悪化を防ぐことができる。
免疫療法は癌に対して有効な治療法の一つではあるが、このような副作用のリスクも伴うため、治療を受ける際には十分に理解し、注意しながら進めていくことが大切である。
一方で、前述の2種の治療法として、抗がん剤治療と免疫療法を組み合わせる方法があるが、効果が期待できる抗がん剤2種類を使った場合でも、効果が続く期間(無増悪生存期間:PFS)はおよそ6ヶ月ほどと考えられている。ただし、免疫療法を組み合わせることで、より長い期間、がんの進行を抑えられる可能性がある。
しかし、免疫療法の効果が長く続くかどうかは人によって違い、必ずしも良い結果が得られるとは限らない。そのため、治療方法を決める際には、病気の進行具合や体の状態をよく考え、最も適した方法を選ぶことが大切である。
免疫療法にはリスクが伴うものの、有効性に期待できるため、2nd line治療の選択肢として検討し、2025年の年明け早々の1月6日に検査及び治療を開始するために父は大学病院に入院した。
入院すぐ肺に溜まった水を抜き、免疫療法の治療が開始となる。
あくる週は両親の結婚記念日であったが、両親は結婚して40年目で初めて結婚記念日を別々に過ごすこととなった。そんな両親を複雑に感じながら、僕の2025年が始まった。
今年は今まであまり向き合えてこなかった父と、改めて向き合う年にしたいと思っている。
次の記事では、父と僕の今までを振り返り、これからして行きたいことを書いていこうと思う。