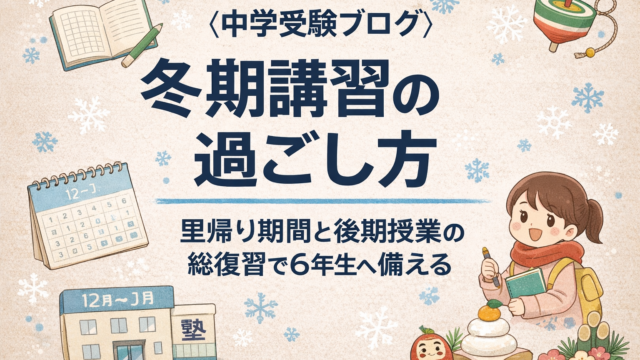はじめに
子育ては親としての責任だけでなく、子どもとの共同生活を通じて多くの学びと成長をもたらします。僕自身、4年生の娘と5歳の息子を育てながら、アドラー心理学の「共同体感覚」という概念に強く共感し、その重要性を実感しています。本記事では、アドラーの共同体感覚について掘り下げ、子育てにおける具体的な体験を交えながらその意味を探ってみたいと思います。
アドラーの共同体感覚とは
アドラー心理学の中核をなす概念の一つが「共同体感覚」です。以前、子供たちの平等に関する記事でも触れたのですが、共同体感覚とは、他者との連帯感や共感、自分が社会に貢献できるという信念を持つことを意味します。アドラーによれば、幸福感や満足感は他者との健全な関係性から生まれるものであり、自分一人の成功や達成感だけでは得られないとされています。
アドラー自身も「共同体感覚」を周囲に理解してもらうにあたって非常に苦心したとの話もあります。そこでアドラーは「共同体感覚」をより具体的な表現にし、「他者への関心」という言葉に置き換え行動指針として示しました。
それは自己への執着から逃れ、他者に関心を寄せることで自ずと「共同体感覚」に到達す流ことができるとしました。この「他者に関心を寄せること」という行動指針は、子育てにおいても非常に重要です。その理由を次で見ていきます。
子育てにおける共同体感覚の重要性
子育ての過程で、子供たちが親の僕たちが理解し難いくだらない遊びに夢中になっていることがよくあると思います。僕ら親はそれを見て「くだらない遊びしているな、、、」とか「そんなことしていないで勉強させたい」などと思うかもしれません。
しかしその遊びである子供たちの関心ごとに対して親がしっかりと「関心を寄せ」「一緒に遊ぶこと」ことで子供たちの共同体感覚を育みます。
子どもにとって、遊びは単なる時間の無駄ではなく、重要な学びの場です。遊びを通じて創造力や社会性、問題解決能力を育むことができます。親がその遊びに対して関心を寄せ、一緒に楽しむことで、子どもは「自分の興味や関心が認められている」と感じることができます。これは、「共同体感覚」を醸成し、子どもの自己肯定感を高め、親子の信頼関係を強化する上で非常に重要です。
共同体感覚を育むための具体的な方法
- 共感的なコミュニケーション
子どもが何かを話そうとする時、その話にしっかりと耳を傾け、共感の意を示すことが大切です。例えば、娘が学校で経験したことについて話す時、私は彼女の気持ちに寄り添い、「それは大変だったね」と共感の言葉をかけるように心がけています。
また当然ですが、スマホを置き、子供たちの方を然りと見て話を聞くように心がけています。(子供たちからの「聞いて聞いて!」は親としてはくだらない話が多くなかなか難儀していますが) - 感謝の気持ちを伝える
家族全員が日常の中でお互いに感謝の気持ちを表現することで、家庭内の共同体感覚が育まれます。娘や息子が手伝いをしてくれた時には、「ありがとう、助かったよ」と感謝の気持ちを伝えるようにしています。
さらに普段から「健康でいてくれてありがとう」や「存在自体に感謝している」ことを伝えたりもするようにしています。 - 問題解決の共同作業
家族で問題や課題に直面した時、一緒に解決策を考えることが重要です。例えば、週末の過ごし方について意見が分かれた時には、全員の意見を出し合い、最善の方法を一緒に考えるようにしています。
特に最近は、娘のショッピングに行きたい希望と息子の虫取りに行きたい希望で別れてしまい、その調整を行うことで子供たちの思考を整理し家族内での共同作業を目指しています。
アドラー心理学における問題行動
アドラー心理学は、問題行動を個人の社会的な文脈と関連づけて理解します。アドラーは、人間の行動は基本的に社会的であり、すべての行動には目的があると考えました。問題行動も例外ではなく、背後には特定の目的や動機が存在します。
子供たちの行動に関しても、子供たちの欲求や社会的(ここでは家族の中で)な文脈に基づいて発生します。アドラー心理学では、これらの行動の背後にある目的や動機を理解し、共感的な対応や相手を受け入れる姿勢を通じて対処することが推奨されています。親や教育者が子どもの問題行動を理解し、適切に対応することで、子どもが健全に成長する手助けをすることができます。
問題行動の特徴
- 注意を引くための行動
子どもは注目を得るために問題行動を起こすことがあります。これは、親や教師からの関心を引きたいという欲求の現れです。こういった行動は、わざと騒がしくする、泣き叫ぶ、いたずらをしたりと親の手を煩わせる行動をとります。ここに見られる欲求としては、子どもは他者からの関心を求め、注目を得たいと感じています。
しっかりと子供に着目して、共感をしてあげましょう。 - 権力争い
権力争いに親を巻き込むことで、自分の存在価値を確認しようとする行動です。これは、親や教師に対して反抗的な態度を取ることが典型です。行動としては、親や教師に対する反抗的な態度、指示に従わない等が挙げられます。ここでの欲求としては、子どもは自己の重要性や独立性を確認したいと感じています。
前項同様に、子供の自立性に対ししっかりと共感し、自己の存在を受け入れてあげましょう。 - 復讐心
子どもが上記権力争いで何の成果も得られなかった場合、問題行動は次のステージへと移ります。自傷行為や非行行動のほか、親に心配をかける行動がそれにあたります。何らかの形で自分(子ども)が傷ついたと感じた時に、他者(親)に同じような苦痛を与えようとする行動です。 - 無能さの表現
さらに自分自身の無能さを装うことで、失敗を避けようとする行動も問題行動の一つとして挙げられます。これは、挑戦を避けるために無力感や無関心を示すことで自分自身の殻に閉じこもり、社会との関係を断ち切ることとなります。
子どもたちとの向き合い方について
こういった問題行動の数々は、自分自身で経験のある人もいれば、身近にそういった人がいるといったこともあると思います。アドラーは「すべての行動には自分自身の意思決定に基づいている」と断言しており、これはすなわち、私たちの行動は他人や環境のせいではなく、自分自身の選択の結果であるということです。この考え方は、問題行動の原因を外部に求めるのではなく、内面的な動機や目的に注目することを促します。
問題行動の内面的な動機と目的
- 自己決定の重要性: アドラー心理学では、すべての行動は自己決定によるものであり、その行動の背後には個々の目的が存在します。例えば、先に記述した子供が注目を引くために問題行動を取るのは、その子供が自分の存在価値を認めてもらいたいと願っているからです。
- 責任の所在: 行動の責任は自分自身にあると認識することは、自己成長の第一歩です。自分の行動を他人のせいや環境のせいにするのではなく、自分の選択と行動に責任を持つことで、より建設的な解決策を見つけることができます。
- 目的論的アプローチ: 問題行動の根本的な目的を理解することで、その行動を変えるための適切な対応策を見つけることができます。例えば、権力争いをする子供には、自己主張の方法を教えたり、適切な場で意見を表現できるようサポートすることが有効です。
実生活での適用
僕たちが実生活でアドラーの理論を活用する際には、以下の内容が役立ちます。
- 観察と分析: 問題行動が発生した際に、その行動の背後にある目的や動機を冷静に観察し、分析することが大切です。例えば、子供が学校で問題を起こした場合、その行動の背景には家庭環境や友人関係が影響していることがあります。
- 共感と対話: 問題行動を示す子供や周囲の人々に対して共感を持ち、オープンな対話を通じて感情や考えを理解する努力をすることが重要です。例えば、子供が叱られたくないと感じている場合、その不安を解消するための対話を試みることができます。
- 具体的な対策: 行動の目的が明らかになったら、具体的な対策を講じることが求められます。例えば、注目を引きたい子供には、勇気づけ行うことが効果的です。
- 自己反省と学び: 最後に、自分自身の行動や反応を振り返り、問題行動に対する適切な対応を学ぶことが必要です。自己反省を通じて、より良い親子関係や人間関係を築くことができます。
アドラー心理学の視点から見れば、すべての行動は選択の結果であり、その背後には必ず目的があります。問題行動に対して適切に対応することで、個々の成長とより良い人間関係を築くことが可能です。親として、また周囲の大人として、子どもたちの行動を理解し、共感と対話を通じてサポートすることが必要です。
まとめ
僕はアドラーの考え方に出会って日常のすべてかかわるような衝撃を受けました。今までは何も考えずに、「いけないことをしたら叱る」「いいことをしたら褒める」と単調だった子育てが一気に複雑化しました。アドラーは叱ることも褒めることも認めません。アドラーはただひとつ共感し、勇気づけを行うことを推奨しました。
この共感に必要なものが共同体感覚で、この共同体感覚は、子育てを通じて私たちが日々感じるものでもあります。親を含めた他人との連帯感や共感を育むことは、子どもたちが社会に適応し、幸福に生きるための基盤となります。
僕自身、娘や息子との関係を通じてこの概念を実践し続けようと努力しています。しかしなかなかうまくいきませんし、時には感情的になることもまだまだあります。ですが、必ず自分自身の成長を伴いながら、親子ともに成長し続けることができると信じています。