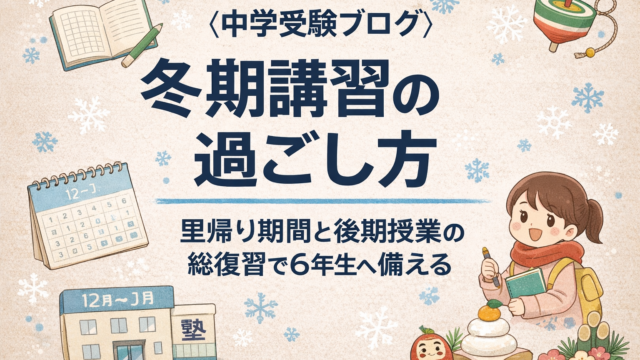僕はこれまで、アドラー心理学に基づく子育てについての僕なりの解釈をブログ記事にしてきました。基本的な知識は、岸見一郎氏著の「嫌われる勇気」や同氏著の「叱らない子育て」に基づき、自分なりの考えを発展させてきました。
今回、新たに岸見一郎氏著の「幸せになる勇気」を読み、自分自身のアドラー心理学の視点のアップデートを行いました。そこには従来の考え方である共同体感覚に加え、愛について深く考える結果となりました。
そこで今回は、愛および結婚生活における対人関係に主眼を置き、夫婦関係やセックスレスの問題に対する考察をしました。
はじめに:アドラー心理学とは何か?
アドラー心理学は、オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーによって創始された心理学の一派で、フロイトの精神分析学派から派生しました。アドラーは人間を個体ではなく、社会的な関係の中で理解することを重視しました。彼の理論は、個人のライフスタイル、目標設定、そして共同体感覚の発達に焦点を当てています。ここでは、セックスレスと夫婦関係の修復方法を岸見一郎の『嫌われる勇気』と『幸せになる勇気』をもとに、アドラー心理学の基本的な概念を紹介しながら解決へ向かっていきたいと思います。
アドラー心理学の基本概念
課題の分離
アドラーは、個人が自分自身の課題と他人の課題を区別することの重要性を強調しました。これにより、不必要な干渉を避け、自己責任を持って生きることが可能になります。『嫌われる勇気』では、この概念が他人によって価値を測定されることの危険性を指摘し、自己受容の重要性を説いています。
『嫌われる勇気』では、「課題の分離」の概念を、他人の問題と自分の問題を明確に区別し、適切に対処することとして解説しています。この概念について具体的な例を引用すると、本書では次のような場面が紹介されています。
例えば、ある親が自分の子供が学校で他の子供たちから受け入れられていないと悩んでいる場面が挙げられます。この親は子供が友達を作ることに一生懸命であるにもかかわらず、子供が孤立してしまっていることに苦しんでいます。この場合、アドラー心理学における「課題の分離」を適用すると、子供が友達を作るかどうかは子供自身の課題であり、親が直接コントロールできるものではないということになります。
アドラーは、親が子供に友達を作るよう強く促すことは、実際には子供の課題に干渉することになり、子供自身の自立を妨げる可能性があると警告します。したがって、親の課題は、子供が自分自身で友達を作るよう励ますことであり、子供がどのようにその課題に取り組むかは子供自身に委ねるべきであるとされます。
この例を通じて、「課題の分離」が人間関係におけるストレスやコンフリクトを減少させるための重要なツールであることが示されています。親として、また一個人として、他人の課題と自分の課題を区別することが、より健全で自立した関係を築く基盤となるのです。
目的論
アドラーの理論の核心にあるのは目的論で、人間の行動は未来の目標に向かって形成されるという考え方です。人は過去の経験に縛られるのではなく、自分が達成したいと思う目標に向かって進むことで行動を決定します。『幸せになる勇気』では、自己実現を目指して前向きな生活を送る方法を探ることに焦点を当てています。
『嫌われる勇気』においてアドラー心理学の中心的な概念の一つである「目的論」は、人間の行動は過去の原因や外的な要因によって決定されるのではなく、自分自身で設定した目標や目的に基づいて自由に選択される、という考え方を指します。この理論を具体的な事例で説明するために、引きこもりの人間が引きこもることを「選択している」という視点が取り上げられています。
引きこもりの事例に見る目的論
『嫌われる勇気』では、引きこもる人々がその状態を選択していると述べられています。これは表面的には被害者的な立場に見えるかもしれませんが、アドラー心理学の観点からは、彼らが引きこもりを選択する背後には明確な目的があると考えられます。この目的は、社会的な期待や失敗、拒絶の恐れから逃れることにあります。引きこもることで、彼らは不安やストレスから一時的に逃れることができ、安全な環境で過ごすことが可能になります。
目的論的解釈
アドラーは、引きこもりという行動が単なる受動的な反応ではなく、その人が何かを達成するための積極的な選択であるとみなします。つまり、引きこもりという行動は「社会からの隔離」や「自己防衛」という目的を果たす手段として選ばれているのです。このような視点は、引きこもりを一種の戦略として捉え、その人が直面している問題に対してより有効に対処する方法を考える上で役立ちます。
目的論と自己責任
目的論は、引きこもりの人々に対しても自己責任を強調します。彼ら自身が自分の現状を変えるための選択を行う能力があると認識することで、彼ら自身がより積極的に自己改善に取り組むことが期待されます。治療や支援を受ける際にも、彼らが自身の行動に対する意図や目的を理解し、それをどのように変化させるかを自ら考えることが重要です。
このように「目的論」は、引きこもりのような社会的問題を個人が自らの意志で変化させるための枠組みを提供します。アドラーの理論は、個人が自分自身の人生の主体者として行動するための強力な支援を提供し、自己実現への道を開くための洞察を与えてくれます。
共同体感覚
アドラーにとって、共同体感覚は心理的健康の最も重要な指標の一つです。これは個人が社会の一員として他者と協力し、共に幸せを追求する能力を指します。『嫌われる勇気』と『幸せになる勇気』の両書では、この共同体感覚を養うことが、より充実した人生を送る鍵であると説明されています。
「共同体感覚」とは、他者との協力と共感を通じて社会に積極的に貢献する意識を指します。この概念は、個人の健康や幸福が他人との関係の質に深く関連しているというアドラーの考えに基づいています。共同体感覚は、自己中心的な行動を超え、他者への奉仕と社会的責任を促進します。
例えば、職場での協力が共同体感覚の一例として挙げられます。自分の所属する企業で、あるプロジェクトの成功のために、個々のメンバーが自己の役割を超えての協力は共同体管轄の情勢につながると考えられています。ここでのポイントは、自分の仕事だけをこなすのではなく、チーム全体の成果を優先する姿勢です。これはアドラーの教える「課題の共有」という概念に基づいており、個人の貢献が集団全体の目標達成にどのように影響するかを理解することを示しています。
岸見一郎によるアドラー心理学の解釈
岸見一郎は、アドラー心理学を現代の日本に適応させ、日常生活で直面する具体的な問題に対する解決策を提供しています。『嫌われる勇気』では、他人からの承認を求めることの弊害と、自己受容を通じた自由な生き方を提案しています。一方、『幸せになる勇気』では、個人が自己実現と社会的幸福の両方を追求する方法に光を当てています。
第1章:アドラーの考える「愛」とは?
愛の定義と心理学的基盤
アルフレッド・アドラーは、愛を単なる感情や情熱ではなく、他者を理解し、共感を持って接する能力と定義しています。アドラーにとって、愛は相互性に基づいており、相手のニーズや感情を尊重し、それに応えることから成り立っています。この章では、アドラーがどのように愛を捉え、それが人間関係にどのように影響を与えるかを掘り下げます。
またアドラー心理学では、自己受容が愛の重要な要素であるとされています。自己受容を深めることで、自分自身だけでなく、他人もそのままの姿で受け入れることができるようになります。この考え方は、人間関係において信頼と安心感を築き上げる基盤となり、健全なパートナーシップを育むために不可欠です。
相手を理解するための共感の重要性
アドラーは、愛における共感の能力を特に重視しています。共感とは、相手の感情や考えを理解し、それに寄り添うことを意味します。この能力は、相手に対する深い理解と尊重をもたらし、それが真の愛情へとつながります。パートナーがお互いにこの共感を実践することで、関係はより強固なものになります。
愛は、行動として表現されることが重要です。アドラーは、言葉や態度、小さな配慮において愛を表現することで、パートナーシップがより充実したものになると述べています。例えば、相手の小さな成功を祝う、励ましの言葉をかける、日々の簡単なサポートを行うなど、日常の中で愛情を具体的に示すことが重要です。
この記事を読んでいただいている方の配偶者には「行動がない!」とか「態度で示してくれない!」などいろいろな配偶者に対するご意見はあると思いますが、この内容については後述していこうと思います。
第2章:共同体感覚と人間関係
共同体感覚の定義
アドラーによれば、共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)は、個人が社会の一員として他者と協力し、貢献する意識を持つことを指します。この感覚は、自己中心的な行動から社会的利益を考える行動へと個人を導きます。本章では、共同体感覚がどのようにして人間関係、特に結婚生活において重要な役割を果たすのかを詳しく探ります。
また共同体感覚は健全な精神状態の基盤とされます。この感覚を持つことで、個人は自己を超えた大きな目的のために行動できるようになり、これが自己実現にもつながります。また、共同体感覚は他者への共感や支援を自然と促進し、これにより人間関係はより密接なものになります。
この共同体感覚の醸成は個人単位では難しいことがわかっており、僕自身もその醸成には、手を焼いています。このアドラーの考えを知らない人たちへ向けて共同体感覚を解くことの難しさ、重要さも痛感しています。
そのため、まずは自分自身や子供たちも含めて「家庭内」という小さな単位での共同体として感覚を養っているところです。(なお、共同体(または社会)の最小単位は、「私とあなた」となります)
共同体感覚の結婚生活への応用
結婚生活において共同体感覚を育むことは、夫婦間の調和と持続的な関係の維持に対して極めて重要です。例えば、共有の価値観や目標を持つこと、お互いの成長と幸福を支え合うことが、この感覚を実現する具体的な方法です。夫婦が共同で問題解決を行うことも、共同体感覚を育む行為の一つです。
僕の場合は、9歳と4歳の子どもたちがいますので、その子たちが成長するさまを夫婦二人で将来に想像を馳せたり、現在励行している資産形成の進捗や10年後のライフプランなどを語り合っています。
社会的利他主義と自己責任
アドラーは、社会的利他主義を共同体感覚の核と見なします。これは、他者への無償の奉仕や支援が個人の幸福感を高めるという考えに基づいています。また、自己責任を持って行動することも重視され、自分の行動が他者に与える影響を常に意識することが求められます。結婚生活においても、これらの原則が夫婦関係の質を高める鍵となります。
社会的利他主義というと何やら難しい概念のように感じますが、「他人のために何ができるか」に帰結しますので、「配偶者のために家事をする」や「子供たちのために食事を作る」といった行為はすべて社会的利他主義となります。
それを義務と捉えるか、自分の幸福感を高めると捉えるかは貴方のこれからの考え方次第になります。この捉え方についても、次の章意向でその考え方についても触れていきたいと思います。
第3章:「与えるためには与えること」の精神
アドラーの与える精神の哲学
アドラーは、「与えるためには与えること」の精神を強調しました。これは、他者に何かを与えることで、間接的に自分自身も豊かな恩恵を受けることができるという考え方です。この精神は、自己中心的な行動を超え、共感と相互支援を基にした関係を築くことを目指します。
SNSが隆盛を極める昨今、自分の正義のみを振りかざし、他者を貶めることに重きが置かれています。さらに自分の意見が発信しやすいSNSでは、自分自身の不幸話に花を咲かせ、共感を得ることを快感に感じる人たちも多く見受けられます。
アドラー心理学では、SNSで多くみられる「悪いあの人」「かわいそうな私」と言った側面には一切触れることなく「これからどうするか」を重要視します。
この考え方が結婚生活にどのように適用され、それがどのようにして両者の幸福に寄与するのかを考えていきましょう。
結婚生活における与えの実践
円満な結婚生活では、「与えること」が夫婦関係の基礎を形成します。これは、日常的な小さな行為から、相手の生活を楽にするための具体的な支援まで多岐にわたります。例えば、相手が疲れているときに家事を引き受ける、相手の趣味やキャリアを支持する、または単に励ましの言葉をかけることなどが含まれます。これらの行為は、相手に対する愛と尊重の表現であり、関係の強化に寄与します。
一方で世間の夫婦関係では「僕は(私は)こんなにやっているのに配偶者は何もしない」等の意見をよく目にします。しかしアドラーは、この考えを明確に否定します。自分自身が仕事を引き受け、相手にも同様の負担を求めること、それは前述の「課題の分離」の原則に反しているとアドラーは主張します。
自分が自発的に行った行為に対して他人に同等の報酬や貢献を期待することは、自分の課題と他人の課題を混同していることになります。このような考え方は、しばしば失望や不満を生む原因となり、夫婦間の不和の根源となることがあります。
アドラーの考え方によれば、個々人は自己の行動や選択に対して全責任を持つべきです。これは、自分が何かを行う際には、それが自分自身の選択であり、自分の内面から来る決定であると認識することを意味します。その上で、他人に対する期待を手放し、彼らが自分の期待に応えなかったとしても平静を保つことが求められます。
夫婦関係においては、このような心構えが非常に重要です。例えば、「私は家事をたくさんしているのに、配偶者は何もしない」と感じる場合、まず自分自身が家事をする理由を見つめ直し、それが本当に自分の内面からの選択であるかを問い直すべきです。家事をすること自体が自分の価値観や幸福感につながる行為なのであれば、それによって得られる内面的な満足感に焦点を当て、配偶者の行動に対する期待を手放すことが有効です。
したがって、お互いに互いのニーズに気を配り、感謝の気持ちを表現することが不可欠です。また、与えることの重要性を認識し、定期的にこの考え方を確認し合うことも、健全な関係を維持する上で効果的です。
第4章:セックスレスの問題と心理学的アプローチ
セックスレスの現象とその心理学的背景
セックスレスは日本において多くの夫婦が結婚生活において直面する問題であり、その原因は多様です。今までの考え方を踏まえるとセックスレスは単なる身体的な問題ではなく、深い心理学的な背景が存在すると考えます。
これには、相互の信頼欠如、コミュニケーションの問題、未解決の対人関係の緊張などが含まれます。この内容は、本ブログ記事のメインテーマとなります。セックスレスが生じる具体的な心理学的原因を探り、自分自身への自答も含めて、今回このテーマに挑戦していきます。
コミュニケーションの役割
セックスレス問題を解決するための最初のステップとしては、オープンで正直なコミュニケーションの確立です。アドラーの言を借りると「すべての悩みは対人関係にある」と言っており、夫婦間の問題も例外ではありません。
夫婦間の感情や期待、懸念を共有することが非常に重要です。そのためには、相互理解を深めるためのコミュニケーションを促進する方法を重視し、これを実践することで関係の改善が期待できます。具体的には、定期的な「夫婦の時間」を設けることや、感情を素直に表現する練習を行うことが有効です。
夫婦関係の修復へ向けて
「そんなこと言ったって既に夫婦関係が破綻しているから今更夫婦の時間なんてあらためて設けることなんでできない!」という声が聞こえてきそうですね。
しかし、その考え方はアドラーに言わせると「貴方がパートナーとセックスしない」ことを決定づけている自分自身の意思とされます。先に述べた引きこもりの子供と同じ「目的論」からくる貴方自身の意思決定であると言えます。
ここで再び、前項で説明した「課題の分離」の考え方が援用されます。「貴方がパートナーと夫婦の時間を確保する」という行為は貴方自身の課題であって、その提案を受け入れるか否かがパートナー自身の課題となります。自分の行動をコントロールすることはできても、パートナーの反応をコントロールすることはできません。重要なのは、提案をすること自体に価値があると認識し、その行動を通じて自分自身の意思を明確に表現することです。
アドラーの理論に基づくと、自分自身で変化を起こす意思がなければ、状況の改善は期待できません。つまり、夫婦関係が破綻していると感じる場合でも、変化に向けた第一歩は自分自身が踏み出すべきです。夫婦の時間を設けることができないというのは、実際にはその選択を自分自身で放棄していることに他ならないのです。
自分の人生において自分自身の幸福は自分の手に委ねられています。これは、夫婦関係においても同様で、自分の行動を変えることで、関係の改善につながる可能性があるとされています。アドラーは、過去のトラウマや原体験による現在の行動制限を明確に否定します。たとえ過去に多くの困難があったとしても、未来に向けて積極的な姿勢を取ることが、最終的には関係の修復や再構築に繋がります。
もし現在の夫婦関係が緊張していると感じているなら、変化を求める努力を始めるのに遅すぎることはありません。小さな一歩から始め、たとえば週に一度のデートナイトを提案するなど、自分から変化を促す行動を取ることが重要です。パートナーの反応は予測できないものの、自分自身が関係の改善を真剣に望むことを示すことで、新たな可能性を創出します。。
まとめ:幸せな結婚生活へのステップ
本記事では、アドラー心理学を基に、愛、共同体感覚、与える精神、およびセックスレス問題へのアプローチを掘り下げました。結婚は、単に二人の生活を共にする以上の意味を持ちます。それは「2人で成し遂げる課題」に取り組む過程であり、「幸せになる勇気」の中でも強調されているように、お互いが成長し、互いの幸せを支え合う場でもあります。以下に、夫婦が共に幸せな結婚生活を築くための具体的なステップをまとめます。
共同の価値観と目標の共有
パートナーと共有する価値観と目標は、関係の土台を強固なものにします。共同の課題に取り組むことで、夫婦はお互いに目標に向かって協力し、それぞれの成果を支え合うことができます。これは、単なる個々の成功を超えて、夫婦としての成長と絆を深めることに繋がります。まずは貴方自身から配偶者に対して、共同の課題を持ち掛け歩み寄ってみてください。そこから必ず何かが変わるはずです。
共同で問題に取り組む
アドラーが提唱する「2人で成し遂げる課題」は、夫婦が共に問題解決を図ることで関係を強化する機会を提供します。セックスレスのようなデリケートな問題も含め、一緒に解決策を見つける過程は、絆を強化し、最終的に夫婦間でお互いに満足度や幸福度を高める結果を享受できます。
このように、アドラー心理学に基づく関係の構築と維持のアプローチは、結婚生活をより豊かで意味のあるものにします。「幸せになる勇気」から学ぶ教訓を活かし、お互いの成長を促しながら、共に幸せを追求することが、成功した結婚の鍵と言えるでしょう。
結婚を決意する際、また結婚後の生活についても「自分はもっと幸せになれる」という視点を持つことは、アドラー心理学においてとても大事なポイントであるといわれています。この観点は、貴方自身が自分自身の成長と共にパートナーシップの質を高めるための原動力となります。以下に、この視点を踏まえた結婚の決意とその実践についての追加の説明を行います。
結婚の決意と個人の成長
僕が何度も繰り返し読んでいる「嫌われる勇気」ならびに「幸せになる勇気」の著者である岸見一郎氏は、結婚を決意した際に「自分はもっと幸せになれる」という信念を持ち結婚に至ったとのことです。
結婚は単なる生活の共有以上のものになります。この信念は、自己実現への道を共に歩むパートナーを選ぶ過程で重要な基準となります。また同著の中でアドラーは「運命の人」の考えを否定しており、人間が未来を自らの手で形成するという「自己決定論」を推奨します。アドラーによれば、「運命の人」という考えは、個人が自己の人生や関係における選択と責任から逃れるための手段として使われがちです。
「運命の人」は過去や運命に委ねるのではなく、自分で関係を築き上げる選択と努力の結果として考え前に進んでいくべきです。これにより、個人はより自律的で意味のある人生を送ることができるようになると考えられています。
日本人に言われる「結婚は人生の墓場である」といった前時代的な言葉は、これからの僕たちの人生には不要な言葉として捉えています。また僕自身も明確にこの言葉を否定したいと思っています。
僕は結婚を通じて、僕と妻の個々の成長を目指し、同時にお互いの幸せを最大化することが目指しています。このことを妻と日々共有しながら、お互いの刺激とし絶えず自己を更新し続ける原動力としていきたいと思っています。
セックスレスが常態化した結婚生活における具体的な実践
「自分はもっと幸せになれる」という観点から、結婚生活においては、お互いの成長を支え合う具体的な行動が求められます。これには、定期的な自己反省と目標設定、お互いの成長や達成を祝う文化の醸成、また互いの趣味や関心事に対する理解と支援が含まれます。これらの実践を通じて、夫婦は結婚を通じての個々の幸せだけでなく、共有された幸せを創出することができると考えられています。
このように、「自分はもっと幸せになれる」という前向きな視点は、結婚生活において両者の幸福感を高め、より充実した関係を築くための基盤となります。結婚は、互いの幸せを追求し、支え合う旅であり、この旅を通じて、夫婦はお互いにとっての最良のパートナーであり続け、家族となり旅の道中で加わった子どもたちという最高の仲間たちと共に進んでいくことができると考えます。
家庭ごとにセックスレスの原因や家庭環境は全く異なることは承知しています。当然、小さな子どもがいる家や思春期の子どもがいる家などでもパートナーに対してのアプローチの仕方は異なってくると思います。
そこで改めて自分に問いかけてほしいことが「これからどうするか」です。「悪い配偶者」や「かわいそうな私」と行った過去の出来事に起因する思考に囚われることなく、「今、この瞬間」を精一杯生きることだけを考えてください。
「今、この瞬間」に自分の人生に悔いはなかったか、素敵な人生と胸を張って言える人生だったかをしっかり問いかけてみてください。
配偶者への恨み言や子どもたちへの小言が最後の記憶なんてさみしいじゃあないですか。そう言った存在への感謝をし、これからの人生をどう生きるかを自分の意志で作り上げていってください。
セックスレスという名前の現象だけみると「自分自身の魅力がないから」や「他に相手がいる」などありもしない邪推が進むこともあるでしょう。しかし、ありもしない事実に気を病むことは止め、「自分はもっと幸せになれる」ことを重要視し、「これからどうするか」を考えていきましょう。
セックスレスの解消は相手あってのことではありますが、解消へ向けての行動を起こすかどうかは、貴方の行動一つです!これからの素敵なパートナーとの生活を応援します!