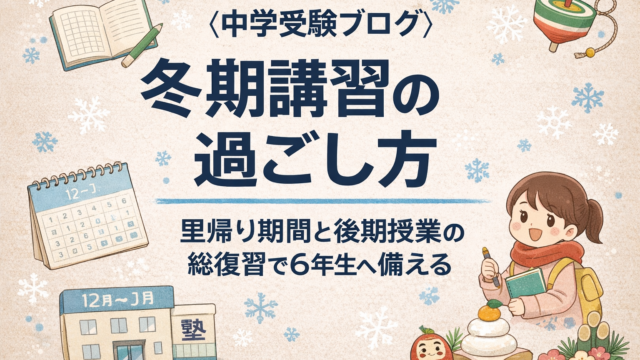勉強しない子どもへの僕のアプローチの仕方について
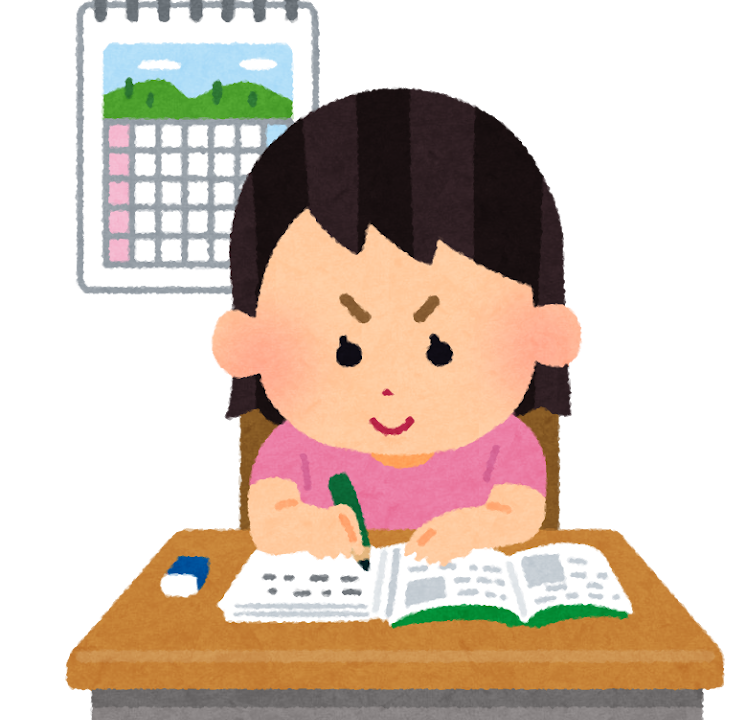
勉強しない子どもへの僕のアプローチの仕方について
僕は、勉強しない娘への僕のアプローチの仕方について、アドラー心理学の考え方を援用しています。今までの記事にも何度か出てきていますが、改めて紹介をしたいと思います。
アドラー心理学とは、オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーによって創始された心理学の一派です。この心理学は、個人が社会的な生活にどのように適応し、共同体の一員としてどのように機能するかに焦点を当てています。アドラーは、人間は生まれながらにして社会的な存在であり、他人との関係の中で成長していくと考えました。
今回はそのアドラーの考えを子育てに活用し、僕自身がどのように娘との関係の構築を目指しているかを書きたいと思います。
僕が推奨する子育てにおけるアドラー心理学の原則
アドラー心理学には、子育てに役立ついくつかの重要な原則があります。たとえば、「勇気づけ」は、子どもが自己受容と他者への共感を学ぶ上で不可欠とされています。このアプローチでは、子どもたち(ひいては対人関係において)物事の結果に対して賞罰を与えるのではなく、子どもの努力と成長を認識し、それを応援することが推奨されています。
9歳の女の子と勇気づけの実践
アドラー心理学で言う「勇気づけ」は、子どもたちに自己受容と他者への共感を育むために非常に重要な方法です。この記事では、僕の娘である9歳の女の子を例にして、どのように日常生活でこの考え方を活かすのかを考えます。
娘の家庭での日常
僕の娘は、前の記事でも紹介した通り失敗をとても恐れる性格でそれゆえに完璧を追い求める几帳面な性格をしています。そのため、物事に興味はあってもチャレンジせずに終わることが多々あります。そういった娘に対して親として最大限んできることとして、今回のアドラー心理学の考えを援用し、娘と向き合っていこうと思います。
親としてのの勇気づけのアプローチ
大切なことは、娘が失敗を恐れずにまた挑戦できるように応援することです。失敗そのものに言及するのではなく、まずは娘の気持ちを受け入れ、親が娘の気持ちに寄り添い共感を示します。
娘が小さい頃から心掛けていたことの例をいくつか挙げてみます。
- 鉄棒など新しいことに挑戦する際に、「出来るように指導」するのではなく「どうやったら出来るようになるのかと一緒に身体を使って考える」
- 自分で料理を作りたいと言った際に忙しくてもなんらかの作業に参加してもらう
- 食事中にふざけてこぼしたとしても、叱らずに食材を無駄にしたことと原状回復の方法を諭す
- 姉弟喧嘩をした際に、双方の言い分を聞きどちらかを叱るのではなく「喧嘩の理由で嫌だったことに共感を示す」ことをし非のある方へはきちんと理由を説明し諭す
娘がすぐに答えにたどり着けない場合でも、模範解答を示すのではなく一緒に考えることで失敗しつつ、失敗を学びの一部として受け入れることができるようにしてきました。
また頭ごなしに叱ることは強権的になり、いうことを聞かせるためには非常に有効かつ簡単です。しかし頭ごなしに叱ることで子供たちは「親は理解者ではない」と認識をしいくつかの問題行動を起こすことにつながります。この問題行動については次に簡単に説明していきたいと思います。
アドラー心理学における問題行動と子供たちの考え
アドラー心理学における問題行動の理解は、個々の行動がどのようにしてその人のライフスタイルや目的に合致しているかを探ることに焦点を置いています。アドラーは、問題行動を単なる「悪い行動」としてではなく、その人が持つ目標やニーズを達成しようとする試みとして見ることを提唱しています。
子どもが行う問題行動は多種多様で、それぞれに背後にある心理的な動機や社会的な影響が存在します。アドラー心理学の観点から見ると、これらの行動は何らかの目的を果たすための手段として行われていることが多いです。以下に具体的な例を挙げて説明します。
学校でのいじめ
子どもがいじめを行う場合、その背後には自己の劣等感を克服しようとする欲求や、他の子供たちとの力関係で優位に立ちたいという欲求が隠れていたり、家庭で注目されないことからせめて学校では注目されたいと思い行動を起こすことがあります。この問題行動は、自己評価を向上させるための非適応的な方法として現れることが多く、自己中心的な目的が反映されています。
家庭内での反抗行動
子どもが家庭内で反抗的な態度を見せる場合、これは自立心の表れや親からの注目を引きたいという目的があるかもしれません。特に親の注意を他の兄弟と分け合う必要がある場合に、注目を集めるための一種の戦略として反抗行動をとる子もいます。
学業の怠慢
学業に対する怠慢や無関心も一種の問題行動とされています。これは学習に対する恐怖や劣等感、あるいは学校の社会環境に対する適応失敗から生じることがあります。子どもは、失敗を避けるために努力をしないという選択をすることがあり、これが問題行動として現れます。
反抗的な言動
反抗的な言動や挑戦的な態度は、親や教師などの権威に対する挑戦として行われることがあります。子どもがこのような行動を取るのは、独自のアイデンティティを確立したい、自らの意見を認めてもらいたいという欲求から来る場合が多いです。
これらの問題行動を理解し対応するためには、単に行動を抑制するのではなく、子どもの感情や要望を理解し、適切な支援と指導を行うことが重要です。アドラー心理学では、これらの行動の背後にある目的や感情を理解し、勇気づけと社会的関心を育むことで、子どもが健全な発達を遂げる手助けをすることを奨励しています。
勇気づけ実践の継続
勇気づけは一度きりのものではなく、日常的なコミュニケーションの中で繰り返し行うべきものであるとされています。娘が次に新たなことに挑戦するときに、小さな成功を積み重ねることで自信を内面から育てていきたいと思っています。
当然、小学4年生になり学校生活では、僕たち親の手の届く範囲を超え成長を続けています。しかし家で行う勇気づけは必ず学校でも生かされると信じています。
課題の分離と子育て
課題の分離とは、子ども自身の問題と親の問題を区別することです。子どもが自身の問題に対処する能力を育てることで、自立心と責任感を養います。この考え方は、子どもが困難に直面した際に、過保護にならず、放任しすぎず適切な支援を行うことが重要ですが、多くの親は子どもの問題を親自身の問題と混同し、子供の問題に対して踏み込みすぎる傾向にあります。つまり「課題の分離」とは、親自身がどの問題が子ども自身のもので、どの問題が親のものかを明確に区分することです。ここでは僕と娘との日常生活から課題の分離の実践方法を探っていきます。
課題の分離と自立を促す子育て
実際に課題の分離といっても、何をすればいいのかわからない方が大多数だと思います。僕自身も暗中模索で、日々格闘をしているところではありますが、現時点での自分なりの考えをまとめたいと思います。
ひとつの例をあげると、今、娘は家で毎日自主学習をすることになっています。(「自主学習を行う」と自ら決めること自体も課題の分離の一つとなります。わけわからなくなってきますよね。)その中で宿題で難しい問題に直面すると、すぐに娘は助けを求めてきます。ここで、僕たち親がどのように対応するかが課題分離のポイントになります。
課題分離のアプローチ
僕たち親は、すぐに正解を教えるのではなく、まずは娘に対して自分で考える機会を与えることが重要になります。たとえば、「もう一度問題を一緒に読んでみようか」と提案し、娘自身が問題解決のプロセスを経験することを支援します。解答へのヒントを少しだけ与えることで、娘が自分の力で解決策を見つけるよう促すことができます。
ここで重要なことは、「自分で問題解決のプロセスを経ること」と前述しましたが、まさにこの「自分で問題解決のプロセスを経ること」が課題の分離にあたります。
宿題をするにあたっての最終的な目標は「答えを書いて提出すること」ではなく、「自分で答えを導き出す能力を身につけること」になります。
この能力を身につけることは、娘の課題であり僕たち親の課題ではないのです。当然ながら僕たちは親として子どもたちの勉強を見る責任はあります。しかし、その親の責任と子どもたちのすべき課題を混同してしまっているのが多くの家庭学習になっていると思っています。
僕自身も親としての課題・娘としての課題を切り分けるのが非常に困難で日々格闘しています。親が勉強を教えるとどうしても「なんで出来ないの!なんでわからないの!」と感情的になりがちですが、ここはしっかり「娘の自立と学習支援が親の課題」「勉強して解答を導き出す能力を身につけることが娘の課題」と課題の分離を行なって感情をコントロールする必要があります。(頭ではわかってるんですけど実践は非常に難しいですね)
課題の分離による自立心の育成
課題の分離の実践は、娘の自立心を育てる重要なステップです。親が適切に娘の課題への挑戦に協力することで、娘は「自分の力で問題を解決できるんだ」という自信を持つようになります。この自信が次第に、他のさまざまな課題に対する取り組み方にも影響を与えると考えています。
長期的な影響
自立心が育つと、他の生活面でも自発的に行動するようになります。たとえば、友達との約束事を自分で管理するようになったり、新しい習い事にチャレンジしたいと自分から言い出すようになり、自身で率先して練習に励むことを行ったりします。これはすべて、日常生活での課題の分離の考えが定着し色々なことを「自分ごと」として認識し始めていることを表しています。
このように、日々の生活の中で課題の分離を意識的に行うことで、娘に対し自分の問題を自分で解決する力を育て、成長する過程での自立を促進することができます。親としては、子どもが自分の力で生きていくためのサポートをしっかりと提供することが求められます。
娘への勇気づけと激励のバランス
勇気づけは、子どもが新しい挑戦に立ち向かうための自信を育むために不可欠です。しかし、過度の勇気づけによる激励はプレッシャーとなり、逆効果になることもあります。親は、子どもが自分自身で目標を設定し、達成する過程を支えてあげることが役割である、と思っています。
僕のこれからの子育てと生活方針について
僕が何気ない日々の読書で出会った岸見一郎著の「嫌われる勇気」は、アドラー心理学という学問の考え方に基づき、僕が子どもたちと向き合う中で大きな転換点をもたらしてくれました。同書には、今まで書いてきた内容はもちろん、対人関係で悩む人々に向けた明確な方針を示してくれています。
アドラー心理学を取り入れた子育ては、僕にとっても子どもたちとの関わり方に新しい視点を提供してくれ、子どもたち自身がが自分と他人を尊重し、協力的で意義のある生活を送るための基盤を築くことができると信じています。
僕たち親がアドラー心理学の原則を理解し、実践することで、より健全な親子関係が築かれ、親子双方の健全な人間関係が築くことができます。
この記事は、アドラー心理学の基本的な概念と、それが子育てにどのように活用できるかを僕と娘を例に挙げて記事にしてみました。本記事をもって皆さんがアドラー心理学に興味を持ち、また子育て中の人たちの心が少しでも軽くなり、親子関係の向上ししすることができたら嬉しいです。