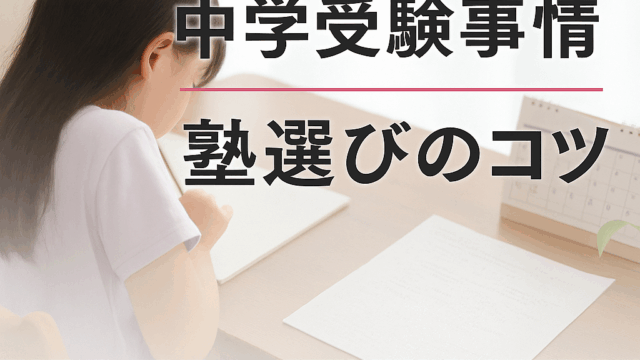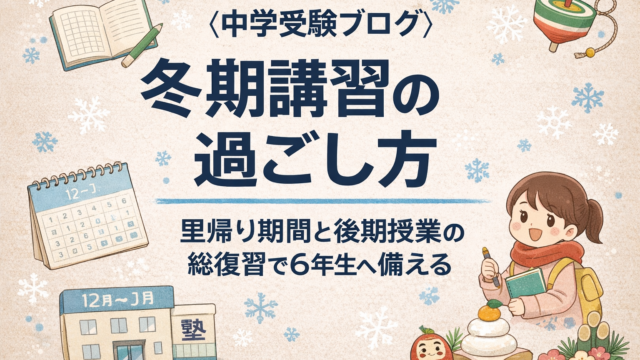【子育ての中での平等とは】小学4年生の娘と4歳の息子の個性の違いを受け入れる方法とは

【子育ての中での平等とは】小学4年生の娘と4歳の息子の個性の違いを受け入れる方法とは
子どもたち一人一人は、それぞれ自分自身の個性・才能を持っています。
僕の4歳の息子は、0歳児クラスから保育園に通っていたこともあり、周囲の人間とのコミュニケーション能力に長け、相手の意図を汲み取ることも得意で、何かに集中しながらでも周りの情報は器用に取り入れるという親バカながら何事も器用にこなす天才肌だと感じています。息子のセンスと柔軟性は、日々の生活や周囲の人たちが息子の手のひらの上で遊ばれているかのようにさえ感じます。
一方、3歳まで僕たち親にべったりで年少さんから幼稚園に通い、現在小学4年生になった娘は、お世辞にも器用とは言えず、相手の意図をくみ取ることや、物事を飲み込むのに少し時間がかかる幼稚園児時代でした。ひとつのことに集中し、それが完璧に仕上がるまで他のことは耳に入らず、出来上がりも完璧でないと気が済まない性格でもありました。
今回は、僕の娘の繊細な性格と僕の娘に対する向き合う姿勢を思考の整理とこれからの想いを交えて書いていきたいと思います。
小学4年生の娘の特性
小さい頃の振り返り
娘は小さい頃から繊細で、確固たる自分のイメージを持ち、ブロック遊びやお絵描きなんかでも自分の持っているイメージが先行で、イメージした通りに仕上がっていないとがっかりしたり、怒ったりと感情の起伏が比較的大きな子でした。
また娘がひとつのことに没頭した時の集中力は、まるで受験生の追い込み時のようで、他の何にも目もくれることなくのめり込んでいます。そういった自分の目指すべき場所をしっかりと見据えて物事に邁進する姿はとても誇らしく思っています。
一方で、このような自分のイメージを先に固めてしまう性格は、娘が未経験の物事や食べたことのないものに対して、必要以上におびえたり、警戒したりする傾向にも現れていて、あまりの不器用さに親として心配になる部分も多々ありました。
娘が初めて挑戦する新しい経験や未知の料理(はじめて出す僕や妻の手料理)に対して、怪訝そうに神経質かつ臆病な反応を示すのを見て、少なからず面食らうことが何度もありました。そのたびに僕たち夫婦は娘が感じる不安を和らげ、新しいことへの好奇心を促すため、事前に食事のメニューと原材料を伝えたり、次に起こり得ることを話したり、いろいろと試行錯誤をしてきました。
その結果、「自分で物事を判断し意思決定する」というスキルが弱まってしまったことも事実です。
小学生に上がってから
僕たち夫婦にとっての初めての子どもである娘の行動は、僕たちにとっては「普通」のことだと思い込んできましたが、2019年に息子が生まれ、姉弟であってもまったく別の特性をもっていることを初めて認識しました。
要領よく物事を受け入れ学んでいく息子と、試行錯誤しながら自分なりに学び進んでいく娘とでは全く別の特性を持っており、両者には独自の感性や個性があることを理解し、双方に対し、その個性を大事に尊重するようになりました。
娘のこのような一面は、親としての僕たちにとって時に大変な挑戦となりましたが、それと同時に娘が持つ豊かな感情の深さや繊細さ、また新しいことへの挑戦に対する彼女なりの慎重なアプローチを理解する機会を与えてくれました。
現在、小学4年生となり親としては「ずいぶん大きくなったものだ」と感慨にふけっていてもまだ幼い子どもです。幼稚園の頃から比べるととても成長し、試行錯誤する方法や時間、判断は格段にスピードアップしています。自分で意思決定できることも増えてきました。しかし、新学期が始まり、環境も変わったことでストレスも大きいことでしょう。そういった小さな変化がとても気になってしまう特性を持っているので、心配しつつも鷹揚に見守っていこうと思っています。
小学生にあがり一歩ずつ、娘は自分の快適ゾーンを広げ、未知の世界に対する恐れを克服していく勇気を見せてくれています。親として僕たちができることは、一歩踏み出そうとするときに背中を押すことと、娘が新たな挑戦に直面したとき・また何か困難に直面したときに安全な避難所となることです。僕は娘の成長を見守りながら、娘が自分自身を信じ、自分の道を歩むことができるように支えていきたいと思っています。
娘の性格と親としての在り方
僕たちも9年間、娘の親をやってきているため、日々の体調の変化や瞬きひとつとっても日常の些細な変化も感じ取ることができるようになってきました。娘の性格上、日々新しいことが起こる日常はとてもストレスだと思っていますし、戸惑うことばかりで大変な思いをしているとも感じています。
大人になって忘れがちですが、僕自身も娘と同じくらいの頃は、ちょっとしたことでおなかが痛くなったり、いやな気分になることは多々ありました。そういったことを家族が見守りつつサポートしてくれ、自分で克服して大人になってきたのだと思っています。
こういった特性は現在ではHSC(Highly Sensitive Child)と呼ばれているそうです。
その反面、「自分自身の娘」となると途端に心配になり娘に対して低い評価をしてしまいがちになります。
心配=低評価でないはずなのですが、僕が娘を心配することにより「娘には出来ない(出来ないかもしれない)」というニュアンスが含まれてしまっているのも事実です。
これを繊細な娘が感じ取り、娘自身の自己評価につながっているのだと考えています。
これは僕にとっても娘にとっても大きな問題であると感じていて、積極的にアドラー心理学でいう「勇気付け」を行うようにしています。しかし、僕自身が娘に対して「心配している」という気持ちを有している事実が娘自身の自己評価の低下につながってしまっていると感じています。
少し話がそれますが、前述のアドラー心理学では「人が人を評価」することを認めていません。
アドラー心理学では、人が他人を評価することは、基本的には認められていません。この理由は、アドラー心理学の中心概念である「共同体感覚」に基づいています。共同体感覚とは、人々が互いに協力し、支援することで社会全体の利益を追求する能力のことを指します。アドラーは、人間は社会的な存在であり、他者との関係の中で成長し、発達すると考えました。
アドラー心理学において、人を評価することは否定的な影響をもたらすとされます。なぜなら、他人を評価する行為は、劣等感や競争心を生み出し、人と人との間に壁を作り出すからです。アドラーは、人間が互いに競争するのではなく、協力し合い、支え合うことでより良い社会を築くことができると信じていました。
また、人を評価することは、その人の価値や能力を一面的にしか見ていないことになり、多面的な人間性や潜在能力を無視することになります。これにより、個人の成長や自己実現の機会を奪うことにもなりかねません。
したがって、アドラー心理学では、他人を評価する代わりに、互いに理解し、支え合うこと、そして個々の人間が自己実現を達成するために、共同体の中で協力し合うことが推奨されています。このような姿勢は、より健全な社会の構築に寄与すると考えられています。
アルフレッド・アドラー
このことを理解しながらもうまく接してあげることができないのは、親として本当に情けなく思っていて、また娘に対して申し訳ない気持ちになります。
娘に対して「なんでもっとうまく立ち回ることができないのか」なんてことは、もはや問う必要はなく、ありのままを受け入れてともに歩んでいくことが重要と考え、努めて娘のよき理解者で娘が安心して寄り添える場所でありたいと思っています。
まとめ
ふたりの子どもを平等に愛し、育てることは非常に難しいと常々感じています。
当然ながらふたりの子供たちを深すぎるほどに愛していて、このふたりの親でいることができてよかった、と心底思えています。
しかし、日常生活のなかで4歳の息子がスムーズにこなすことが、小4の娘にとっては一苦労。娘が時間をかけて成し遂げることが、息子にとっては一瞬の出来事。このような特性の違いを理解し、受け入れることは、親として大きな課題に直面しています。
僕たち大人はしばしば、平等とは同じように扱うことだと考えがちですが、それは誤解かもしれません。子どもたちが持つ個々の才能や興味、挑戦に対するアプローチを理解し、それぞれに合ったサポートを提供することが、真の平等であると考え始めています。
息子の自由奔放な発想を尊重しつつ、娘の細部に対するこだわりを認める。もちろん親からの評価という形ではなく、子どもたち自身が自信をもって意志を持つことができるよう勇気づけを行う形で。それぞれの個性を輝かせるために、息子には広い視野で物事を見る力を、娘には急がずにゆっくりと成果を目指す心を育てる。そうすることで、二人の子どもたちは互いに異なる道を歩みながらも、同じくらいの愛情を感じることができると思って接してきたいと思います。
子育ては、姉弟間での公平を求められながらも答えのない難易度の高い旅路です。形式的な平等ではなく、娘・息子がお互いに納得してそれぞれの個性を最大限に引き出すことの応援がしたいと心から思っています。
子育て中の人たちとブログやX(旧Twitter)こういった意見や葛藤を共有できていければ嬉しいです。
X(旧Twitter)でも情報発信をしています。