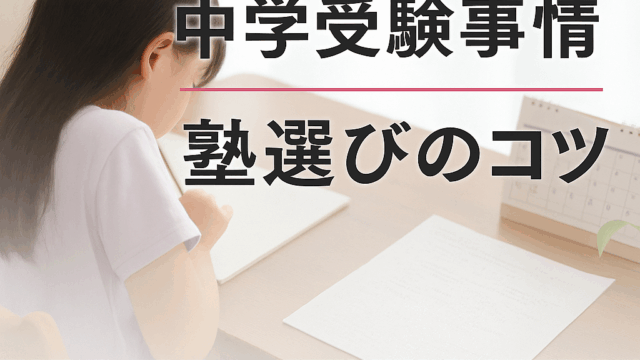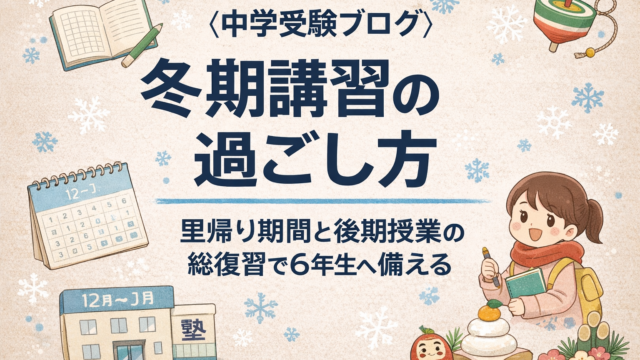保育園に通う4歳の息子が「ひらがな」を自発的に学び始めた、ただひとつの方法

保育園に通う4歳の息子が「ひらがな」を自発的に学び始めた、ただひとつの方法
まず、プライベートな話から入ってしまい大変恐縮ですが、僕は転職を重ね、テレワークも含めて子供達との時間がとても多く取れる環境で仕事ができています。
上の娘はこの春から小学4年生。9歳になりだいぶ手がかからなくなりましたが、やはり子育ては毎日が新しい発見があり、子どもたちの成長は僕自身も親として成長ができる素晴らしい学びの機会であると感じています。
特に言葉の習得に関しては、子どもたちの世界を劇的に広げる重要な学びと痛感しています。
今回は、僕の4歳の息子がひらがなを自発的に学び始めた方法についてお話しします。この方法は、保育園に通う4歳の息子が「ひらがな」を自発的に学び始めた、ただひとつの方法として僕がお伝えできるアイデアです。
周りの子たちが読める用になっていくのにひらがなが読めるようにならなかった息子
息子と同じ保育園に通う子供たちは、少しずつ新しい字を覚え、ひらがなをサラサラと読み進める子もや、中には既にひらがなを書くことができる子もいました。しかし、息子はひらがなが読めるようになるその一歩を、なかなか踏み出せずに過ごしていました。
息子は文字に全く興味がなく、図鑑を読んでいても絵で覚えて字を必要としませんでした。自分の名前ですら読めないという状況でした。
僕は、息子の文字への興味・執着のなさがどうしても心配になり、文字に興味を示すよう、さまざまな方法を試しました。かるた、アプリ、絵本、文字積み木…しかし、息子にとってのひらがなは、まるで興味を引かないただの記号でした。
それでも、僕は諦めずに息子がひらがなに興味がないという事実を受け入れ、息子のペースで進むことを決意しました。いつでもひらがなに触れることができるよう身の回りにひらがなのポスターを張ったり、手の届く範囲に音が出るひらがなの絵本を置いてみたりと、考えうる限りのことをしました。
5歳の間近に控えた2024年にあっても、息子の文字への興味は変わりませんでした。しかしそんなある日、息子は「アンパンマンの音絵本」で遊び始めたのです。このことは文字に興味のなかった息子にとって、大きな一歩でした。
僕はその瞬間を祝い、息子も「文字に興味を持つことがいいことなのか?」と言わんばかりに「アンパンマンの音絵本」で遊ぶことに自信を持つようになり、丁寧にひらがなと触れ合っています。
僕は、保育園のほかの子たちがひらがなが読めても、ひらがなが書けても、自分の焦りや気持ちは息子には伝えないようにしていました。もちろん、ひらがなが読めないことは、決して恥ずかしいことではないですし、日本人の識字率を考えると読めないままでいるわけはないのです。それぞれの子供が持つ個性とペースを大切にし、一緒に成長していくことが何よりも重要と改めて感じました。
5歳上のお姉ちゃんの同じ時期と比べてもひらがなを読めるようにならなかった息子
息子は、もうすぐ5歳。同じ年齢の時にはもうひらがなの読み書きができていたお姉ちゃんと比べると、まだ自分の名前はおろか、一文字も読むことができません。この事実は、僕にとって大きな悩みの種でした。
親として、子どもたちを公平に見ることは大切だと頭ではわかっていても、心はつい比較してしまいます。
お姉ちゃんは、絵本が大好きで絵本に書いてある記号(文字)について、早くから興味を持ち、夜寝る前に一緒に絵本を読むのが日課でした。しかし、息子は絵本を見ることは好きですが、文字にはあまり関心を示しません。絵本に書いてあるキャラクターや出来事に興味津々です。一方で登場人物の機微や心情の変化・動機については非常に敏感に感じ取っていました。
僕は、息子が文字に興味を持ち、図鑑を自分自身で読み始める日を心待ちにしています。その日が来れば、息子の世界は爆発的に広がると思っているからです。しかし、それと同時に、息子はお姉ちゃんとは違う個性を持っていることを尊重しなければならないとも思っています。彼は彼のペースで成長していくのですから。
親としては、子どもたちが同じように成長してほしいと願うものですが、それぞれが異なる才能や興味を持っていることを忘れがちです。息子がひらがなを読めるようになる日を楽しみにしつつ、今、ゆっくりと、しかし急速に成長していく姿を横で眺めながら共に過ごす時間を大切にしたいと思います。
親としての心構え
僕の息子は、もうすぐ5歳になりますが、まだひらがなを読むことができません。お姉ちゃんは3歳ですでにひらがなを読むことができ、4歳では書くことができていました。幼稚園と保育園の差、と言ってしまえば身も蓋もないですが、同じ年齢でできていたことしては対照的です。
息子の保育園の同級生たちも、多くはすでに読み書きを始めています。親として、どうしても比較してしまいがちですが、アドラー心理学における「勇気づけ」の概念は、僕にとって息子との関係性についてに大切な教訓を教えてくれます。
勇気づけとは何か
勇気づけとは、困難に立ち向かい、乗り越えるための活力を与えることとされています。これは、単なる褒め言葉ではなく、子どもたちが自分の能力を信じ、挑戦を続けるための支援です。勇気づけは、成功や失敗に関わらず、子どもたちの努力を認め、子どもたちの自立心を育てます。
勇気づけの実践
息子がひらがなに興味がなく読めない代わりに、彼の興味を持つ活動を通じて、学ぶ楽しさを教えることができます。例えば、息子が好きな恐竜の図鑑を使って、文字を学ぶゲームを作るなどです。これは、息子にとっての「勇気づけ」となります。息子のペースを尊重し、自分の道を見つけるのを支援することが重要となります。息子がひらがなに興味を持つようになるまで、焦らずに待つことも勇気づけの一環です。息子の成長を信じ、息子が自分のペースで学ぶことを応援するつもりです。(どんなにテレビに齧り付いていても、、、)
親としての心の整え方
もちろん、親として、子どもたちの成長に対する期待は自然なことですが、それぞれの子どもが持つ独自のタイミングがあることを受け入れることが大切です。息子がお姉ちゃんや同級生と異なる成長を遂げることは、息子は息子の特別な人生を歩んでいる証と考えます。僕たち親は、その人生を温かく見守り、必要なときには手を差し伸べることで子供たちの自尊心を育み勇気づけを行うよう努めたいと思っています。
結論
まさに今、ひらがな学習の途中にある息子と生活して改めて実感することは、自分自身の心の棚卸しがとても大事であるということです。
僕自身の経験に基づく子どもの成長はお姉ちゃんである娘の時のものだけであって、息子には当てはまらないこと、また「3歳ではひらがなに興味を示すはずだ」とか「4歳にはひらがなか書けるようになるはずだ」と言った情報は、当然のことではあるものの一度息子とは別に考える必要があるということです。
色々と息子の好奇心を刺激し、文字への興味を引いたりしましたが、タイミングというものは突然訪れます。僕は、親として子どもが楽しみながら自然と興味を持ったら学ぶことができる環境を整えることの大切さを感じています。
それが今回は、興味のある恐竜の図鑑でもなく、ひらがな積み木でもなく、全くテレビではみたこともない「アンパンマン」の音絵本でした。子育てはいつ、何がきっかけで突然前に進むかわかりませんね。
また子どもたちの成長は比較するものではなく、子どもたちそれぞれの成長を喜び見守り、応援することと改めて認識することができました。僕が好んで引き合いに出す「アドラー心理学」における勇気づけを通じて、子どもたちが自分自身を信じ、自分の力で歩んでいく力を育てていきたいと思っています。
子育て中の人たちとブログやX(旧Twitter)こういった意見や葛藤を共有できていければ嬉しいです。
X(旧Twitter)でも情報発信をしています。